特集│HR KEYWORD 2022 つながる Z世代 “Chill&Me”で理解するZ世代 原田曜平氏 信州大学 特任教授
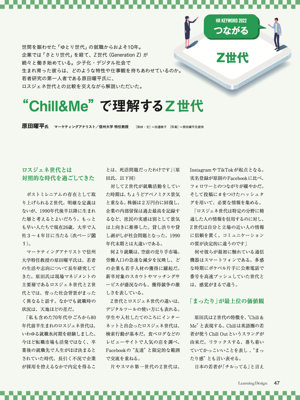
世間を賑わせた「ゆとり世代」の就職からおよそ10年。
企業では「さとり世代」を経て、Z世代(Generation Z)が続々と働き始めている。
少子化・デジタル社会で生まれ育った彼らは、どのような特性や仕事観を持ちあわせているのか。
若者研究の第一人者である原田曜平氏に、ロスジェネ世代との比較を交えながら解説いただいた。
ロスジェネ世代とは対照的な時代を過ごしてきた
ポストミレニアムの存在として取り上げられるZ世代。明確な定義はないが、1990年代後半以降に生まれた層と考えるとよいだろう。もっとも早い人たちで現在26歳、大卒で入社3~4年目に当たる(図1)。
マーケティングアナリストで信州大学特任教授の原田曜平氏は、若者の生活や志向について長年研究してきた。原田氏は現場マネジメントの主要層であるロスジェネ世代とZ世代とでは、育った社会背景がまったく異なると話す。なかでも就職時の状況は、天地ほどの差だ。
「私も含めた70年代中ごろから80年代前半生まれのロスジェネ世代は、いわゆる就職氷河期を経験しました。今ほど転職市場も活発ではなく、卒業後の就職先で人生がほぼ決まるとされていた時代、長引く不況で企業が採用を控えるなかで内定を得ることは、死活問題だったわけです」(原田氏、以下同)
対してZ世代が就職活動をしていた時期は、ちょうどアベノミクス景気と重なる。株価は2万円台に回復し、企業の内部留保は過去最高を記録するなど、庶民の実感は別として景気は上向きに推移した。貸し渋りや貸し剥がしが社会問題となった、1990年代末期とは大違いである。
何より就職は、空前の売り手市場。労働人口の急速な減少を反映し、どの企業も若手人材の獲得に躍起だ。新卒対象のスカウトやマッチングサービスが盛況なのも、獲得競争の激しさを表している。
Z世代とロスジェネ世代の違いは、デジタルツールの使い方にも表れる。学生や入社したてのころにインターネットと出会ったロスジェネ世代は、検索行動が基本だ。食べログなどのレビューサイトで人気の店を調べ、Facebookの“友達”と限定的な範囲で交流を重ねる。
片やスマホ第一世代のZ世代は、InstagramやTikTokが起点となる。実名登録が原則のFacebookに比べ、フォロワーとのつながりが緩やかだ。そして投稿に#をつけたハッシュタグを用いて、必要な情報を集める。
「ロスジェネ世代は特定の分野に精通した人の情報を信用するのに対し、Z世代は自分と立場の近い人の情報に信頼を置く。コミュニケーションの質が決定的に違うのです」

