第2回
アリストテレスの「中庸」 坪谷邦生氏 株式会社壺中天 代表取締役/壺中人事塾 塾長
品川皓亮氏 株式会社COTEN歴史調査チーム/「日本一たのしい哲学ラジオ」パーソナリティ/元弁護士
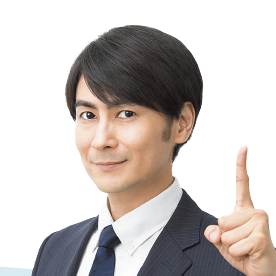 坪谷邦生氏
坪谷邦生氏
「人を生かして事をなす」ための思考のフレームワークを人事・哲学の専門家である坪谷邦生氏と品川皓亮氏に伺う本連載。
不透明で正解のない時代、二者択一を迫られ、悩むことも多い人事パーソン。そこで今回、取り上げるのはアリストテレスが唱えた「中庸」だ。「極端に偏らず、過不足なく調和がとれていること」を指す概念である。時を超えて伝わる“究極の経験則”を意思決定に結びつけるには―。
[取材・文]=西川敦子 [写真]=坪谷邦生氏、品川皓亮氏提供
極端と極端の間にある“最適な一点”を探れ
―― 「中庸」を唱えたのは古代ギリシャの哲学者、アリストテレス(紀元前384~紀元前322年)とのことですが、どういう人だったのでしょう。
品川:
古代ギリシャの哲学者というと、ソクラテスやプラトンが有名ですよね。アリストテレスはプラトンの弟子。若い時から非常に優秀で、プラトンが創設した学校、アカデメイアに鳴り物入りで入学してきたといわれています。
あらゆる学問を研究しており、プラトンが説いた哲学「イデア論」はもちろん、倫理学や論理学、政治学、生物学、物理学、さらに天文学にも精通していました。今回の「中庸」は彼の著書『ニコマコス倫理学』に登場する概念。ちなみに、ニコマコスはアリストテレスの息子の名前といわれているんですよ。
彼は動植物から政治まで、いろんな事物、現象を徹底的に観察しました。観察したことを抽象化し、そこから理論を組み立てていたのだと思います。
「あらゆるものは何かになる可能性を秘めている」というのがアリストテレスの持論でした。たとえば植物の種って、ただの丸くて固い謎の物体じゃないですか。でも実は美しい花を咲かせる可能性を持っている。
どんな状態なら可能性が開花するのか。種なら土の中にある方がいいし、魚だったら水の中にいるのが一番ですよね。では、人間の可能性を最大化してくれるものは何かといえば、理性ではないか。理性こそ、人間の特徴だと彼は考えました。
―― 理性を働かせることで人間が人間らしく開花すると。
品川:
そうです。人間が本当に幸福になるためには「アレテー(徳・卓越性)」を磨かなければならない。アレテーを磨くには、理性を働かせなければならない、というのがアリストテレスの思想でした。理性を働かせるうえで具体的な指針として挙げたのが「中庸」です。幸福な生き方の秘訣と言い換えることもできますね。
―― 中庸……。聞いたことはありますが、何を意味する言葉なんでしょう。
品川:
極端な方法を採らず、最適な一点を選択するのが中庸です。アレテーを実現して生きようとしたとき、極端を選択するのは悪であるとアリストテレスは論じています。人間が理性を発揮してアレテーを実現し、幸福に近づいていく道は両極の間にあるはずだ、と。
ここで思い出してほしいのが昔話「桃太郎」です。もし、桃太郎がひとりきりで、しかも丸腰で鬼ヶ島に乗りこんだとしたらどうでしょう。無謀な戦いを挑んだところで、鬼が相手では負けるでしょうし、死ぬかもしれない。逆に臆病になり、「やめとくわ、なんだか怖いし」と鬼退治をあきらめてしまったら、「何のために川から流れてきたんだ?」ということになる。つまり、「無謀」も「臆病」も極端なんです。
だったら理性を働かせ、両者の間にある「勇気」を選べばいい。イヌ、サル、キジという味方がいれば勝算はあります。2つの極端の間のちょうどいいところにあるのが勇気、つまり中庸なのです。

