OPINION2 外せないのは、3つの柱と5つのディシプリン 学びたい欲求の阻害要因を取り除くため「学習する組織」に必要なこと 小田 理一郎氏 チェンジ・エージェント 代表取締役社長 兼 CEO
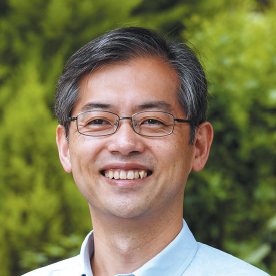 小田 理一郎氏
小田 理一郎氏
いま、多くの企業は学習障害に陥っている―そう警鐘を鳴らすのは、人材育成や組織開発、チェンジ・マネジメントのための研修やコンサルティングを手掛ける小田理一郎氏だ。
学習障害から脱却し、組織全体としての学習能力を高めるため、注目したいのが「学習する組織」の考え方である。そのような組織は、どうすれば構築することができるのか。概要や要諦について、話を聞いた。
[取材・文]=平林謙治 [写真]=小田 理一郎氏提供
変われない組織に潜む「学習障害」
企業人事、特に採用担当者なら誰もが思うだろう。「優秀な人材が1人でも多くほしい」と。
しかし、個々のメンバーがいくら優秀でも、組織としての成果を生み出せるとは限らない。むしろ優秀であるがゆえに、それぞれが持つノウハウや成功体験にとらわれやすく、自分たちが理解している範囲内での対症療法やトラブルシューティングのみに終始してしまう。環境変化への適応に遅れ、後手に回りがちな組織の“あるある”だ。
変化に翻弄されて、求める結果が得られないのは、変化の不確実さや激しさ以上に、それを正しく学んでいない、学ぼうとしていない問題が大きい。つまり「組織に学習障害が生じているからだ」と、チェンジ・エージェント代表の小田理一郎氏は喝破する。
「新規事業やイノベーションの創出にはトライアンドエラーの積み重ねが欠かせません。にもかかわらず、組織の風土が失敗に厳しかったり、成果を急ぎすぎたりすると、それがプレッシャーとなって学びを抑圧し、無難なことしか考えられなくなってしまう。変革がうたわれながら実現に至らない企業に、よく見られる学習障害です。また、接客業でいうと、苦情や不具合を訴える顧客に対して真摯に向き合わず、それこそ“カスハラ”のひと言で安易に片づけてしまうような組織も学習障害を疑うべきでしょう。そこに潜む本質的な問題や市場の変容に気づく機会を、自ら逃しているわけですから」
このような学習障害から脱却し、組織は組織全体としての学習能力を高めなければいけない。そこで注目したいのが「学習する組織(Learning Organization)」だ。これはマサチューセッツ工科大学のピーター・センゲ博士らが提唱した組織開発の理論である。同博士の薫陶を受けた小田氏は、日本における第一人者として、20年ほど前から「学習する組織」の普及推進を図ってきた。
学びの旅は“無知の知”から始まる
「学習する組織」とは何か。どんな組織を指すのか。小田氏は、<目的に向けて効果的に行動するために、集団としての意識と能力を継続的に高め、伸ばし続ける組織>と定義する。
「学習する」というと、知ることやわかること、つまり知識を得る行為を連想するが、「学習する組織」の実践に重要なのは、知識より上述の定義にある「意識」だと、小田氏は指摘する。
「ここでいう意識(アウェアネス)とは、“気づく”ことを意味します。気づくことは“知る”“わかる”と関係してはいますが、必ずしも一致しません。むしろ自分ではわかっていたつもりが、実はわかっていなかったことを悟ったり、自分が何を知らないかを知って、それを真摯に受け止めたりできる状態に誘(いざな)うのが、気づくということ。気づかないまま努力したり、能力を高めようとしても、成果には結びつきにくいでしょう。気づき=意識は、能力発揮の大前提ともいえるのです」
世界が直面する環境変化は極めて複雑であるにもかかわらず、私たちの認知や合理性はごく限られた範囲にしか及ばない。「自分たちがいかに知らないか」という現実に気づけるかどうか。“無知の知”とよばれる謙虚な姿勢こそ学習の基本であり、「学習する組織」を目指す旅の始まりなのだ。
もっとも、その旅にゴールはなく、小田氏も「学習する組織そのものに特定の完成形はない」と強調する。
では、どのようにしてそれを構築すればよいのか。小田氏によると、センゲ博士は「3つの中核的な学習能力と、それを構成する5つのディシプリン」を提示し、それらをバランス良く伸ばしていくことが重要と説く。

