第22回 在宅勤務導入で、気をつけることは? 藤原英理氏 あおば社会保険労務士法人 代表
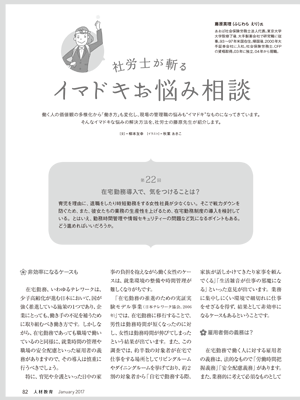
働く人の価値観の多様化から「働き方」も変化し、現場の管理職の悩みも“イマドキ”なものになってきています。
そんなイマドキな悩みの解決方法を、社労士の藤原先生が紹介します。
第22回 在宅勤務導入で、気をつけることは?
育児を理由に、退職をしたり時短勤務をする女性社員が少なくない。そこで戦力ダウンを防ぐため、また、彼女たちの業務の生産性を上げるため、在宅勤務制度の導入を検討している。とはいえ、勤務時間管理や情報セキュリティーの問題など気になるポイントもある。どう進めればいいだろうか。
非効率になるケースも
在宅勤務、いわゆるテレワークは、少子高齢化が進む日本において、国が強く推進している施策の1つであり、企業にとっても、働き手の不足を補うために取り組むべき働き方です。しかしながら、在宅勤務であっても職場で働いているのと同様に、就業時間の管理や職場の安全配慮といった雇用者の義務がありますので、その導入は慎重に行うべきでしょう。
特に、育児や介護といった日中の家事の負担を抱えながら働く女性のケースは、就業環境の整備や時間管理が難しくなりがちです。
「在宅勤務の推進のための実証実験モデル事業(日本テレワーク協会、2006年)」では、在宅勤務に移行することで、男性は勤務時間が短くなったのに対し、女性は勤務時間が伸びてしまったという結果が出ています。また、この調査では、約半数の対象者が在宅で仕事をする場所としてリビングルームやダイニングルームを挙げており、約2割の対象者から「自宅で勤務する際、家族が話しかけてきたり家事を頼んでくる」「生活雑音が仕事の邪魔になる」といった意見が出ています。業務に集中しにくい環境で細切れに仕事をせざるを得ず、結果として非効率になるケースもあるということです。

