巻頭インタビュー 私の人材教育論 個人の“知”を集め、「いい匂いのする」ソリューションを生む

神戸製鋼とIBM。2つのものづくり企業のDNAを受け継ぎ、新たな変革にチャレンジするコベルコシステム。その卓越したソリューション力は、「いい匂いがする」と顧客から評価されている。同社の「勝ち残り」を賭けた人財育成は、個を活かし、同時に全社にまたがるネットワーク力を活かす、という基本方針に基づく。その要諦と想いを聞いた。

“継承と変革”が育成のポイント
――日本の企業社会は東日本大震災、原発事故などにより、今まさに正念場を迎えています。どんな思い、決意を持ってこの国難に臨もうとお考えでしょうか。
奥田
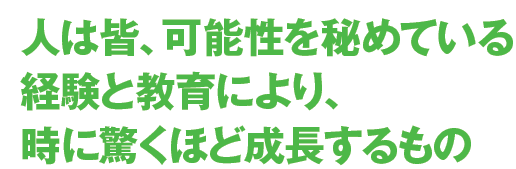
このたびの震災に直面し、日本人が見せた姿勢に、世界から多くの賛辞が寄せられました。ひとたび国難が起これば、一体となって危機に立ち向かう国民であることを改めて、認識した人も多かったことでしょう。
津波によって富やインフラは一瞬にして失われましたが、日本人の精神、祖先から受け継いだ遺伝子は失われなかったのです。
一方、歴史を振り返れば、日本人は変化を受け入れ、新しい文明を生み出す力も持っていることがわかります。明治維新、戦後の復興など、私たちはさまざまなパラダイムシフトを乗り越えながら、新しい時代を創造してきました。
企業においても同じではないでしょうか。どんな時も危機意識を持ち、前を向いて変革を起こしていく。「復興」という大きな課題を前に、企業は改めて、この責務を認識すべきでしょう。今こそ現場感覚を持つ企業が先頭に立ち、新しい時代を築く時です。この国難を転機とすべく、腰を据えて復興に取り組まねばなりません。
―そんな時代において、人材育成とは。
奥田

人こそが経済を推し進めるエンジンであり、厳しい時だからこそ、最も力を入れるべきことだと考えています。特にIT企業の場合、社員一人ひとりの能力が、全てを支えるといっても過言ではありません。ですから、当社では人財育成を最重要テーマとしてやってきました。「不易流行」――不変の真理を知って基礎を確立し、変化を知って進展を遂げる――という松尾芭蕉の言葉がありますが、当社らしさを守り継ぎつつも、変革すべきところは変革し、育成システムを進化させてきました。
成長すると見える景色が変わる!
――人材育成について、具体的にどんな信念をお持ちですか。
奥田
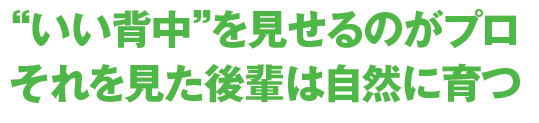
人は誰しも大きな可能性を秘めています。最初からレッテルを貼ってはなりません。何を経験させ、教えるかによって時に驚くほどの成長をとげるからです。
成長することで、活動のステージを一段、また一段と登ることができます。すると見える景色が変わる。視野が広がり、今まで突き当たっていた問題が小さく見えます。そして、付き合う人も変わります。これは楽しいですよ。仕事をするうえでの、1つの醍醐味といえるのではないでしょうか。
私自身、入社した当初にいきなり現場に放り込まれ、業務システムの設計を担当したことを覚えています。何分、青二才だったので赤くなったり青くなったりの連続でしたが(笑)、お客様の業務システムをITが大きく変えていく様を目の当たりにし、システムの重要性や戦略的な価値はすごいものがあるということを痛感しました。そして、そのようなシステムを設計するプロフェッショナルとして、お客様により一層貢献するためにはどうすればいいかを考える機会にもなり、この業界での私の原点となっています。こうした経験を社員にも、ぜひ味わってほしいですね。

