巻頭インタビュー 私の人材教育論 伸びるのは、好奇心を胸に何事にも学ぶ、輝きを持つ人材
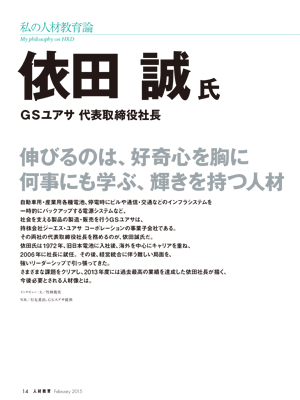
自動車用・産業用各種電池、停電時にビルや通信・交通などのインフラシステムを一時的にバックアップする電源システムなど、社会を支える製品の製造・販売を行うGSユアサは、持株会社ジーエス・ユアサ コーポレーションの事業子会社である。
その両社の代表取締役社長を務めるのが、依田誠氏だ。
依田氏は1972年、旧日本電池に入社後、海外を中心にキャリアを重ね、2006年に社長に就任。その後、経営統合に伴う難しい局面を、強いリーダーシップで引っ張ってきた。
さまざまな課題をクリアし、2013年度には過去最高の業績を達成した依田社長が描く、今後必要とされる人材像とは。

さらなる飛躍のテーマ
──ジーエス・ユアサ コーポレーション全体として、第三次中期経営計画の初年度(2013年度)は上々の立ち上がりでした。今後の見通しについては、どのようにお考えですか。
依田
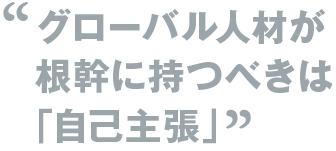
おかげさまで2013年度は、売上高および営業利益、経常利益が過去最高となりました。2004年に旧日本電池と旧ユアサコーポレーションが経営統合して以来、10年が経過しています。これまでが経営統合の是非を検証する期間だったとすれば、まず成功と言ってよいでしょう。これを受けて次の10年では、さらなる飛躍をめざすことになります。
──自動車・二輪車用の鉛蓄電池では国内トップシェア、世界でも第2位のGSユアサが今後めざす企業像とは。
依田

ひと言で表すなら「エネルギーデバイスカンパニー」です。エネルギーをつくり、貯めて、社会に供給していく。エネルギーの効率的活用が、よりシビアに求められるこれからの社会において、重要な役割を担う企業集団への転換を図ります。第三次中期経営計画は、そんな思いを込めて練りました。
もう少し具体的に言えば、省エネ、創エネ、蓄エネを3本柱に据えた企業、ということです。
今のところ我々の基幹事業は、鉛蓄電池です。リチウムイオン電池が話題となっていますが、当社の売上構成で見れば10%程度にとどまります。ただ、今後の成長の糧がリチウムイオン電池であることは明らかであり、鉛とリチウムを成長の両輪として、マーケットに合わせた組織改編に取り組んでいきます。
──どう組織を変える予定ですか。
依田
そもそも鉛蓄電池とリチウムイオン電池では、生産と流通の仕方が違います。鉛蓄電池は基本的に地産地消型、需要のある地域で製造供給するのが効率的です。対してリチウムイオン電池は装置産業型の商品です。高度に機械化を進めた工場が必要なため、初期投資にそれなりの額が求められます。
したがってリチウムイオン電池では、一定の販売量を確保したうえで生産体制を構築しないと採算が取れません。そこで、より大きなマーケットを狙うのに、グローバル化は必然の流れとなります。
現在、当社には国内の事業部とは独立した形で国際事業部があります。鉛蓄電池主体の事業体制であればこれでよかったのですが、今後、リチウムイオン電池事業を伸ばしていくためには、グローバル化のレベルを一段階引き上げる必要があると考えています。
グローバル人材の本質
──グローバル化を進めていくとなれば、求められる人材も変わってくるのではないでしょうか。
依田
地産地消体制なら、中国で販売する製品は中国でつくり、インドネシアでつくったものは現地で売るわけです。この体制では、日本で働く従業員と海外の従業員が交流する機会はまずないでしょう。ところがグローバル化を進めれば、国による垣根はなくなります。海外から日本に来て働く人が出てくるだろうし、逆のパターンも増えてくるはずです。
── 最近は大学でも「グローバル人材」育成を目標に掲げるところが増えています。GSユアサではどのような人材を求めているのでしょうか。
依田
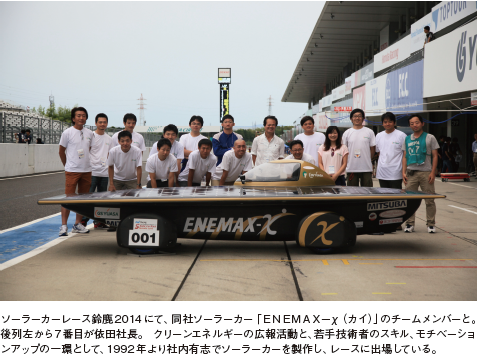
まず、グローバル人材とは何かを改めて考え直す必要があります。グローバル人材と言えば、一般的には語学力と、海外で暮らしていける精神的なタフネスなども注目されているようです。

