巻頭インタビュー 私の人材教育論YKK 代表取締役社長猿丸雅之 世界を舞台にやり抜く人材を育てる現場体験と言葉の力

小さな部材、ファスナーで世界シェア45%(金額ベース)を誇るYKKは「小さな巨人」といえるかもしれない。約70の国と地域にまたがる拠点へ、入社早々の若手たちが自ら志願し、果敢に飛び出していくという同社。そんな同社のグローバル人材の育成はどのような方針に基づいているのだろうか。

“現場”を与えるため海外に若手を出す
――ファスニング事業の海外進出の歴史は古く、1959年のニュージーランド社設立からと伺っています。早くからグローバルに事業を展開されてきた理由は何だったのでしょうか。
猿丸
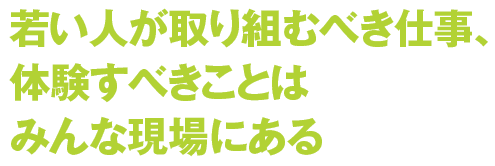
現在、当グループの生産拠点は世界約70の国と地域に広がっています。世界の事業エリアは日本、北中米、南米、東アジア、EMEA(ヨーロッパ、中東、アフリカなど)、ASAO(アセアン、南アジア、オセアニアなど)の6つのブロックに分けており、地域ごとの特性を活かしながら「世界6極地域体制」を展開中です。ただ、当社の計画に沿って生産拠点を広げようとしたわけではなく、結果として広がっていっただけなのです。ご存知のように縫製業は労働集約型産業です。したがって非常に早い時期より、欧米からアジアを中心とする新興国へと生産移転が行われてきた。それに伴い当社も、早くから生産拠点をグローバルスケールで展開させてきました。
というのも、ファスナーという部材は、縫製資材の中でも最後に注文されるものなので、どうしても短納期が要求されます。そのため縫製工場のすぐ近くで生産しなければならないという宿命がある。ですから、当社も世界中のマーケットを追い求めて展開を続けてきたのです。
――貴社は特にグローバル志向の就職活動生の間で人気企業と聞きます。
猿丸

確かに、若いうちから海外赴任する社員が多いのは当グループの特徴ではないかと思いますね。世界3万9000名のグループ従業員のうち、日本からの海外赴任者は約600名。32、33歳にもなれば、もう一通り海外での経験を積んでいるという人間が少なくありません。
おかげで新人にも、海外志向が強い人が集まってきます。3年目になってまだ日本にいたりすると「いつになったら出してくれるんですか」と文句をいってくる社員もいるくらいです(笑)。
赴任希望先も、少し前まで欧米がほとんどだったのが、最近はインドネシア、インド、バングラデシュなどのアジアの国々が目立つようになった。未知の可能性を秘めた国で思いきり腕試ししたい、と考えるのでしょう。近頃の若者は内向き志向と聞きますが、少なくとも当社ではそういった風潮はあまり見られません。
――若手を積極的に海外赴任させるのはなぜでしょうか。
猿丸
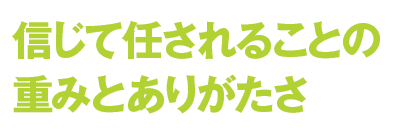
彼らに“現場”を与えたいからです。縫製産業の現場はアジアを中心とする海外にありますからね。YKKの場合、新人は入社3年目まで。年齢を四捨五入して30代が若手、40代が中堅と人材の層を分けています。それ以上は「余人をもって代えがたい人材になれ」と話しています。「新人や若手を一人前」にし、「余人をもって代えがたい人材」に育てるものは何かといえば、それは現場に他なりません。若い人が取り組むべき仕事、体験すべきことはみんな現場にあります。
どのように注文が入り、生産し、納品するのか。どのように縫製作業に組み込まれ、販売されるのか。みんな現場に行って、直接見聞きしなくてはならないことです。机上で知った気になっているだけではだめなのです。
私も米国赴任時代、こんなことがありました。あるお客様の工場から午後4時に急に注文が入った。そしてなんと、その日のうちに納品してくれという。めちゃくちゃな話です。
どういうことかと思いその縫製工場に駆けつけてみると、そこでは注文を午後3時に締め切っていた。それから資材を発注して揃え、翌朝8時から生産を開始するというんです。そういう事情がわかれば、こちらも何とか対応しなければと思うし、スムーズな発注納品の方法のご提案もできます。それもこれも現場に行けばこそできることで、行かなければわからないまま。現場が全てを教えてくれるんです。
本社勤務の時には予想もしなかったような体験をすることもあります。同じく米国時代、倉庫担当が休むと私が彼の代わりにフォークリフトを運転したりしていました(笑)。小規模の支店業務では、1人抜けるとマネジャーでも身体を動かして穴埋めせざるを得ないんです。

