ヤオハン倒産を振り返って 倒産から学ぶ5つの教訓
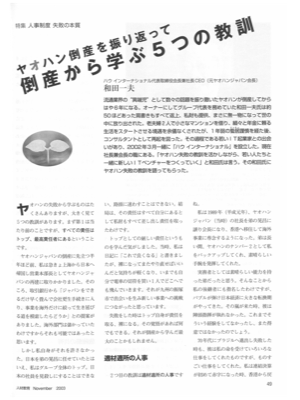
ヤオハンの失敗から学ぶものはたくさんありますが、大きく見て5つの教訓があります。まず第1は当たり前のことですが、すべての責任はトップ、最高責任者にあるということです。
ヤオハンジャパンの倒産に先立つ半年ほど前、私は急きよ上海から日本へ帰国し営業本部長としてヤオハンジャパンの再建に取りかかりました。そのころ、取引銀行から「ジャパンをできるだけ早く畳んで会社更生手続きに入り、事業を海外だけに絞って生き延びる道を模索したらどうか」との提案がありました。海外部門は儲かっていたわけですからそれも可能ではあったと思います。
しかし私自身がそれを許さなかった。日本を弟の晃昌に任せふヽだとはいえ、私はグループ全体のトップ。日本の社員を見殺しにすることはできない、路頭に迷わすことはできない。結局は、その責任はすべて自分にあるとして私財もすべて差し出し責任を取ったわけです。
トップとしての厳しい責任というものを学んだ気がしました。当時、私は日記に「これで良くなる」と書きましたが、裸になってまたやり直せばいいんだと気持ちが軽くなり、いまでも自分で電車の切符を買い1人でどこへでも飛んでいきます。それが九州の飯塚市で出会いを生み新しい事業への挑戦につなかったと思っています。
失敗をした時はトップ白身が責任を取る、裸になる。その覚悟があれば何でもできる。それが倒産から学んだ最大のことかもしれません。
適材適所の人事
2つ目の教訓は適材適所の人事ですね。
私は1989 年(平成元年)、ヤオハンジャパン(当時)の社長を弟の晃昌に譲り会長になり、香港へ移住して海外事業に専念するようになった。弟は長い間、ヤオハンのナンバー2として私をバックアップしてくれ、素晴らしい手腕を発揮してくれた。
実務者としては素晴らしい能力を持った弟だったと思う。そんなことから私の後継者にも指名したわけですが、バブルが弾け日本経済に大きな転換期がやってきた。その嵐が来た時、彼は陣頭指揮が執れなかった。これまでそういう経験をしてなかったし、また得意ではなかったのでしょう。

