新連載 「偶然」からキャリアをつくる 第1回 「デザイン通り生きるのではなく、 生きながらデザインしていく」
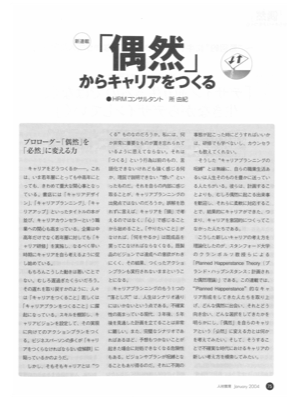
「CTIジャパン」は、日本におけるコーチ養成機関の草分け的存在である。そして、CTIジャパンの代表である榎本英剛氏のキャリアを見ると、“Planned Happenstance ” の代表者にも思える。彼のこれまでのキャリアを見ながら、どのような「偶然」とどう向き合い、それをどのように活かしていったのかを考えてみよう。
プロローグー「偶然」を「必然」に変える力
キャリアをどうつくるか――。これは、いま若年層にとっても中高年にとっても、きわめて重大な関心事となっている。書店には「キャリアデザイン」、「キャリアプランニング」、「キャリアアップ」\といったタイトルの本が並び、キャリアカウンセラーという職業ぺの関心も高まっている。企業は中高年だけでなく若年層に対しても「キャリア研修」を実施し、なるべく早い時期にキャリアを自ら考えるように促し始めている。
もちろんこうした動きは悪いことでない。むしろ遅過ぎたくらいだろう。その遅れを取り戻すかのように、人々は「キャリアをつくること」若しぐは「キャリアプランをつくること」に躍起になっている。スキルを棚卸し、キャリアビジョンを設定して、その実現に向けてのアクションプランをつくる。ビジネスパーソンの多くが「キャリアをつくらなければならない症候群」に陥っているかのようだ。
しかし、そもそもキャリアとは“つくる” ものなのだろうか。私には、何か非常に重要なものが置き忘れられているように思えてならない。それは「つくる」という行為以前のもの、言語化できないけれども強く感じる何か、理屈で説明できない“想い” といったものだ。それを自らの内部に感じ取ることが、キャリアプランニングの出発点ではないのだろうか。誤解を恐れずに言えば、キャリアを「頭」で考えるのではなく、「心」で感じることから始めること。「やりたいこと」がなければ、「何をやるか」は既成品を買ってこなければならなくなる。既製品のビジョンでは達成への意欲がわきにくく、その結果、つく勹たアクションプランも実行されないままということになる。
キャリアプランニングのもう1つの“ 落とし穴” は、人生はシナリオ通りにはいかないという点である。不確実性の高まっている現代、3年後、5年後を見通した計画を立てることは非常に難しい。また、完璧なシナリオであればあるほど、予想もつかないことが起きた場合に対処できなくなる危険性もある。ビジョンやプランが呪縛となることもあり得るのだ。それに不測の事態が起こった時にどうすればいいかは、研修でも学べないし、カウンセラーも教えてくれない。
そうした“キャリアプランニングの呪縛”とは無縁に、自らの職業生活あるいは人生そのものを豊かに送っている人たちがいる。彼らは、計画することよりも、むしろ偶然に起こる出来事を歓迎し、それらに柔軟に対応することで、結果的にキャリアができた、つまり、キャリアを意図的につくってこなかった人たちである。
こうした新しいキャリアの考え方を理論化したのが、スタンフォード大学のクランボルツ教授らによる「Planned Happenstance Theory (ブランド・ハップンスタンス:計画された偶然理論)」である。この連載では、“Planned Happenstance ” 的なキャリア形成をしてきた人たちを取り上げ、どんな偶然に出会い、それとどう向き合い、どんな選択をしてきたかを明らかにし、「偶然」を自らのキャリアという「必然」に変える力とは何かを考えてみたい。そして、そうすることで不確実な時代におけるキャリアの新しい考え方を模索してみたい。
子供時代~仕事や会社に対する疑問~
榎本氏の「働くこと」に対する問題意識は、既に子供時代に芽生えていた。30 年前の日本の父親の多くがそうであったように、榎本氏の父もまた、私生活よりも仕事を優先して働く「滅私奉公」型のサラリーマンだった。そんな父を見て、そもそも人はなぜ働くのかという素朴な疑問を持つようになる。というのも、「一生懸命働きながらも、父が幸せそうには見えなかった」(榎本氏)からだ。「大人になったいまでは理解できる部分も多いが、子供の目には家族のために自分を犠牲にして働く父の姿は不思議に映った。それが仕事とは何か、会社とは何かを考える出発点だった」と榎本氏は語る。
少年時代の夢は「建築家」。家の間取りを考えることが好きで、実家を新築する時には、海外に単身赴任中だった父に代わって、自らが設計を担当した。榎本氏は「いま思うと、自分で何かをデザインすることにものすごく興味があった」と言う。
学生時代~ ワーキングホリデーで出会った最初の「偶然」~
高校・大学時代は、まだ将来の職業生活を具体的に思い浮かべることができず、「サラリーマンにだけはなりたくない」という漠然とした気持ちしかなかった。
大学ではボート部に所属。就職シーズンになると、ボート部のOBが学生をリクルーティングするために合宿所を訪れる。そして、大きな大会を控えた大学4年生たちは、ろくに会社訪問もせず、OB の話を聞いて就職先を決めていった。当時大学3年生だった榎本氏はそんな先輩たちの姿に大きな疑問を抱く。「人生の一大事をそんな受け身の状態で決めていいのかと思った。といって、自分には何かやりたいことが明確にあるわけでもなかった」。そんな彼が選んだのは、海外に行くこと。そして、それは後に彼が経験する数多くの「憫然」との出会いの端緒となる。
ワーキングホリデーを利用して、オーストラリアに渡った榎本氏は、そこで「初めて世の中の厳しさを知った」と言う。それは見知らぬ土地で自分の生活をかけて働くという、学生のアルバイトとは異なる体験だった。だれも助けてくれないので、自分の道は自分で切り開かなければならない。主にウェイターの仕事をしていた彼はある日、より時給の高い店を探しにホテルのレストランに行く。結局、そこで仕事を得ることはできなかったが、その代わり、たまたま居合わせた日本人から、「日本人観光客向けのツアーガイドの仕事ならある」と言われる。
「人前で話をするのは苦手。でも、ガイドの仕事は昼間なので、夜のウェイターの仕事と掛け持ちすることができるのでやってみることにした」(榎本氏)。やってみると意外な発見があった。1つは、人前で話をすることは結構楽しいという発見。もう1つは、人をガイドするのが好きだということだ。
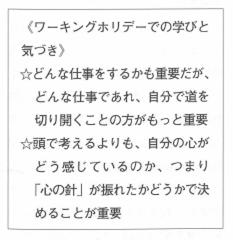
それまで経験したことのない仕事、しかも苦手だと思っていた「人前で話す仕事」をなぜ引き受けたのか。榎本氏は少し考えてから、「心の針が振れたから」と答えた。つまり、できるかできないかを考えるのではなく、やってみたいかどうかを自分に問いかけて、[やってみたい] という答えが自分から返ってきたというのだ。「心の針」が振れたことが、彼をツアーガイドの仕事にチャレンジさせた。そして、「やってみたいことなら、苦手だと思っていることも克服できるだろうと思った」(榎本氏)。

