連載 人材と組織の強みを活かすAl 第3回 AI- 5 つの原則
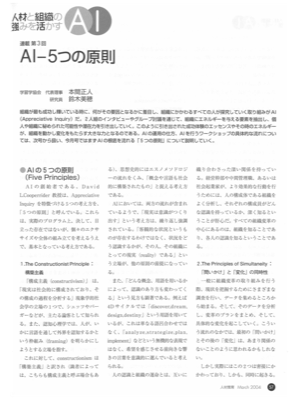
組織が最も成功し輝いている時に、何がその要因となるかに着目し、組織にかかわるすべての人が探究していく取り組みがAl(Appreciative Inquiry) だ。2人組のインタビューやグループ討議を通じて、組織にエネルギーを与える要素を抽出し、個人や組織に秘められた可能性や潜在力を引き出していく。このように引き出された成功体験のエッセンスやその時のエネルギーが、組織を動かし変化をもたらす大きな力となるのである。 AIの運用の仕方、AI を行うワークショップの具体的な流れについては、次号から扱い、今月号ではまずAI の根底を流れる「5つの原則」について説明していく。
AIの5つの原則 (Five Principles)
AI の創始者である、DavidL.Cooperrider 教授は、Appreciative Inquiry を特徴づける5つの考え方を、「5つの原則」と呼んでいる。これらは、実際のプログラム上、決して、目立った存在ではないが、個々のエクササイズや全体の組み立てを考えるうえで、基本となっている考え方である。
1 .The Constructionist Principle :
構築主義
「構成主義(constructivism)」は、「現実は社会的に構成されており、その構成の過程を分析する」現象学的社会学の立場の1つで、シュッツやバーガーなどが、主たる論客として知られる。また、認知心理学では、人が、いかに言語を通して外界を認知するかという枠組み(framing) を明らかにしようとする立場を指す。
これに対して、constructionism は「構築主義」と訳され(識者によっては、こちらも構成主義と呼ぶ場合もある)、思想史的にはエスノメソドロジーの流れをくみ、「概念や言語も社会的に構築されたもの」と捉える考え方である。
AI においては、両方の流れが含まれているようで、「現実は意識がっくり出す」という考え方は、繰り返し強調されている。「客観的な状況というものが存在するわけではなく、状況をどう認識するかが、その大、その組織にとっての現実(reality) である」という立場が、他の原則の前提になっている。
また、「どんな概念、用語を用いるかによって、認識のあり方も変わってくる」という見方も顕著である。例えば4D サイクルでは「discover,dream,design,destiny 」という用語を用いているが、これは単なる語呂合わせではなく、「analyze,strategize,plan,implement 」などという無機的な表現ではなく、希望を感じさせる前向きな響きの言葉を意識的に選んでいると考えられる。
人の認識と組織の運命とは、互いに織り合わさった深い関係を持っている。経営幹部や中間管理職、あるいは社会起業家が、より効果的な行動を行うためには、人の構成体である組織をよく分析し、それぞれの構成員がどんな認識を持っているか、深く知るということが肝心だ。すべての組織変革の中心にあるのは、組織を知ることであり、各人の認識を知るということである。
2 .The Principles of Simultaneity :
「問いかけ」と「変化」の同時性
一般に組織変革の取り組みを行う際、現状を把握するためにさまざまな調査を行い、データを集めるところから始まる。そして、そのデータを分析し、変革のプランをまとめ、そして、具体的な変化を起こしていく。こういう流れのなかでは、最初の「問いかけ」とその後の「変化」は、あまり関係のないことのように思われるかもしれない。

