連載 「偶然」からキャリアをつくる 第3回 「眠っている遺伝子を目覚めさせ、 チャンスをつかむ」
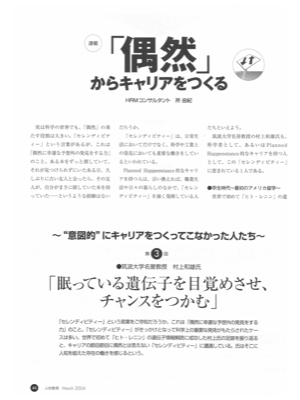
「セレンディピティー」という言葉をご存知だろうか。これは「偶然に幸運な予想外の発見をする力」のこと。「セレンディピティー」がきっかけとなって科学上の重要な発見がもたらされたケースは多い。世界で初めて「ヒト・レニン」の遺伝子清報解読に成功した村上氏の足跡を振り返ると、キャリアの節目節目に偶然とは思えない「セレンディピティー」に遭遇している。氏はそこに人知を超えた存在の働きを感じるという。
実は科学の世界でも、冂禺然」の果たす役割は大きい。「セレンディピティー」という言葉があるが、これは「偶然に幸運な予想外の発見をする力」のこと。ある本をずっと探していて、それが見つけられずにいたある日、久しぶりに古い友人と会ったら、その友人が、自分がまさに探していた本を持っていたーーというような経験はないだろうか。
「セレンディピティー」は、日常生活においてだけでなく、科学や工業上の発見においても重要な働きをしているといわれている。
Planned Happenstance 的なキャリアを持つ人は、言い換えれば、職業生活や日々の暮らしのなかで、「セレンディピティー」を強く発揮している人たちといえよう。
筑波大学名誉教授の村上和雄氏も、科学者として、あるいはPlanned Happenstance 的なキャリアを持つ人として、この「セレンディピティー」に恵まれている1人である。
学生時代~最初のアメリカ留学~
世界で初めて「ヒト・レニン」の遺伝子情報解読に成功した村上氏の科学者としてのスタートは、ノーベル賞を受賞した湯川博士と同じ大学(京都大学)に進みたいという希望を抱いた高校時代。しかし、両親の勧めで入学した高校は進学校ではなく、十分な受験勉強ができないまま、京都大学を受験しかところ、「まぐれで合格した」(村上氏)。「京大には毎年1~ 2名はたまたま受かってしまう“落ちこぼれ”がいるが、私もその1人だった」という。最初は自分と同じような学生かいることを知ってほっとしたが、周囲の多くの秀才と自分を比べて、村上氏は次第に劣等感を持つようになる。
あこがれの大学に入ったものの、パッとしないまま学部、大学院と進んだ村上氏は、博士課程を修了した時、教授の薦めで渡米する。 1963年、ポートランドにあるオレゴン医科大学での留学経験は、村上氏にとって大きな刺激となり、「それまで眠っていた遺伝子が目覚めた」(村上氏) という。留学生といっても、授業料を払って講義を受けるという立場ではなく、当時、アメリカの大学が盛んに行っていた「ポスト・ドクター制度」による留学だったため、給料をもらって研究するという恵まれた環境。「自由競争の雰囲気が自分の肌に合った」(村上氏) ことから、のびのびと研究に打ち込むことができた。
学園紛争~2 度目の渡米~
オレゴン医科大学での研究は2年で終わり、村上氏は帰国して京大の助手となる。その当時、囗本の大学には学園紛争の嵐が吹き荒れていた。「大学立法」を巡って、京大でも学生と大学側との対立は日増しに激しくなっていた。「助手は学生と教授の間にいる微妙な立場」(村上氏) で、年齢的には学生に近く、共感することも多かったことから、結局は、教授職と助手職の対立という構図になっていく。
村上氏も「大学立法」に反対する立場として、仲間たちと“教授追及会”の開催を決意する。ところが、会の直前になって多くの学生・助手が離脱。村上氏も悩んだ末にアメリカに「逃げた」(村上氏)。このことは、村上氏の心にずっと影を落とし、「敵前逃亡したみたいでずっとやましい気持ちがあった」という。
1969 年にナッシュビルのバンダービルト大学の医学部に渡った村上氏の決意は、1回目の留学とは異なるものだった。「日本にはもう帰るまいと思った。仮に帰国したとしても、京大はもちろん、大学には戻らないと考えていた」(村上氏) という背水の陣。また、最初の留学のような「ポスト・ドクター制度」による“お客様”的な存在ではなく、今度は、他の研究者と競争していかなければならなくなった。
アメリカの大学では、教える側も生徒から評価を受ける。過去にどんな業績をあげていても、学生から「つまらない講義」と評価されれば、次の年度にはポストを失ってしまう。村上氏の場合は、学生から「英語がダメで講義が下手だと言われていた」(村上氏)。研究の方でも目覚ましい成果を上げることができず、悩む日々が続いていた。
レニンとの出会い
ところで、村上氏の研究室の近くに、スタンレー・コーエンという教授の研究室があった。コーエン教授は後にノーベル賞(医学賞・生理学賞) を受賞することになる研究者だが、この時点では「風変わりで冴えないおじさん」( 村上氏) だったという。そのコーエン教授か、ある日、村上氏の部屋を訪れて、「血圧の上昇にかかわる物質を発見したかもしれない。一緒に研究をしないか」と言う。村上氏は自分の研究に行き詰まっていた時でもあったので、この申し出を引き受けることにする。これが、その後、村上氏にとって生涯の研究テーマとなる「レニン」との出会いの第一歩であった。
コーエン教授と村上氏は、血圧上昇作用を持つ物質を取り出し、結晶化する実験に取り組んだ。もしその物質が特定できれば、高血圧の治療に役立つ情報を得られるかもしれない。そうした使命感にかられ、実験を進めていくうちに、コーエン教授の“発見” は間違いたったことが判明する。彼が「血圧を上げる物質かもしれない」と思ったもののなかには、微量ながら不純物が混じっており、その不純物が血圧上昇に深くかかわっていたのである。
それは腎臓に含まれている「レニン」という酵素と同じ働きをするもので、マウスの顎下腺(唾液腺)から抽出したことから、村上氏とコーエン教授は「頷下腺レニン」と名づけた。
「レニン」とは酵素の1つで、ホルモンを作り、それを使って血圧を上げる機能を持つもの。 19世紀末からその存在は知られていたが、多くの科学者が純粋なレニンを取り出すことに挑んでは、失敗するという歴史があった。医学界では「レニンには手を出すな」と言われるくらい“厄介な”物質として知られていたが、農芸化学出身の村上氏はそのことは知らず、「手を出した後で知った」(村上氏)。
これまでの失敗の記録はほとんど残っていないので、分野の異なる村上氏には知りようがなかったのだが、それと同時に、「レニンの研究は面白そうだ」というインスピレーションがわいたという。この2つが村上氏を「レニン」に取り組ませるきっかけとなった。

