連載 人材と組織の強みを活かすAI 第5回 AI 実践のプロセスーDream
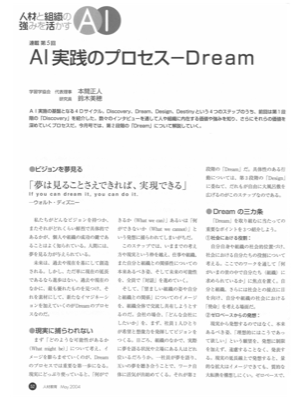
AI実施の基盤となる4Dサイクル。 Discovery、Dream 、Design 、Destiny という4つのステップのうち、前回は第1段階の「Discovery 」を紹介した。数々のインタビューを通して人や組織に内在する価値や強みを知り、さらにそれらの価値を深めていくプロセスだ。今月号では、第2段階の「Dream 」について解説していく。
ビジョンを夢見る
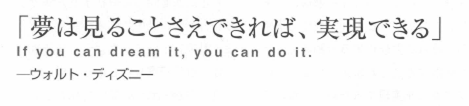
私たちがどんなビジョンを持つか、またそれがどれくらい鮮烈で具体的であるかが、個人や組織の成功の鍵であることはよく知られている。人間には、夢を見る力が与えられている。
未来は、過去や現在を基にして創造される。しかし、ただ単に現在の延長であるなら進歩はない。過去や現在のなかに、最も優れたものを見つけ、それを素材にして、新たなイマジネーションを加えていくのがDream のプロセスなのだ。
現実に捕らわれない
まず「どのような可能性があるか(What might be )」について考え、イメージを膨らませていくのが、Dreamのプロセスでは重要な第一歩になる。現実にどっぷり使っていると、「何かできるか(What we can) 」あるいは「何かできないか(What we cannot)」という発想に捕らわれてしまいがちだ。
このステップでは、いままでの考え方や現実という枠を越え、仕事や組織、また自分と組織との関係性についての本来あるべき姿、そして未来の可能性を、全員で「対話」を進めていく。
そして、「望ましい組織の姿や自分と組織との関係」についてのイメージを、組織全体で交流し共有しようとするのだ。会社の場合、「どんな会社にしたいか」を、まず、社員1人ひとりが希望と想像力を発揮してビジョンをつくる。日ごろ、組織のなかで、実際に夢を語る状況や立場にある人はどれ位いるだろうか。一社員が夢を語り、互いの夢を聴き合うことで、ワーク自体に活気が出始めてくる。それが第2段階の「Dream 」だ。具体性のある行動については、第3段階の「Design」に委ねて、だれもが自由に大風呂敷を広げるのがこのステップなのである。
Dream の三ヵ条
「Dream 」を取り組むに当たっての重要なポイントを3つ紹介しよう。
①社会における役割:
自分自身や組織の社会的位置づけ、社会における自分たちの役割について考える。ここでのワークを通して「何かいまの世の中で自分たち(組織)に求められているか」に焦点を置く。自分と組織、さらには社会との接点に目を向け、自分や組織の社会における「使命」を考える場面だ。
② ゼ囗ベースからの発想:
現実から発想するのではなく、本来あるべき姿、「理想的にはこうであって欲しい」という願望を、発想に制限を加えず、遠慮することなく、発表する。現実の延長線上で発想すると、量的な拡大はイメージできても、質的な大転換を構想しにくい。ゼロベースで、自由にイマジネーションを膨らませるところが、Dream のポイントだ。
③自由に話せる心理的に安全な環境:
一般に「Dream 」というのは個人的なものと思われがちだ。しかし、これを組織全体が共有すると、大きな推進力が生まれる。
そこで第2段階では、自由に発想を広げ、何を言ってもいいという心理的に安全な環境をつくる。
夢を組織全体で共有するコミュニケーションのプロセスを確保することが重要なのだ。夢を語るというと、「そんな馬鹿げたこと(crazy dream) を考えていたのか」、とは思われたくないので、他人に理想を語るのを手控える人が多い。だからこそ、心理的に自由に語れる環境をつくることが、きわめて重要なのだ。

