連載 誌上コンサルティング 第43回 人事部から各部門・関係会社主導の 人材育成に転換するには
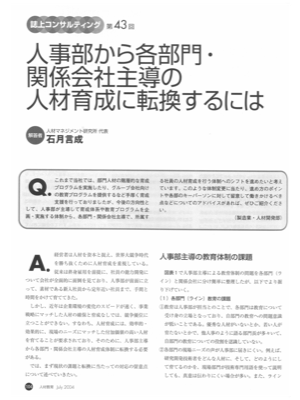
Q.
これまで当社では、部門人材の階層的な育成プログラムを実施したり、グループ会社向けの教育プログラムを提供するなど手厚く育成支援を行っておりましたが、今後の方向性として、人事部が主導して育成体系や教育プログラムを企画・実施する体制から、各部門・関係会社主導で、所属する社員の人材育成を行う体制へのシフトを進めたいと考えています。このような体制変更に当たり、進め方のポイントや各部のキーパーソンに対して留意して働きかけるべき点などについてのアドバイスがあれば、ぜひご紹介ください。
(製造業・人材開発部)
A.
経営者は人材を資本と捉え、世界大競争時代を勝ち抜くために人材育成を重視している。従来は終身雇用を前提に社員の能力開発について会社が全面的に面倒を見ており、人事部が前面に立って、素材である新入社員から定年近い社員まで、手間と時間をかけて育ててきた。
しかし、近年は企業環境の変化のスピードが速く、事業戦略にマッチした人材の確保と育成なしでは、競争優位に立つことができない。すなわち、人材育成には、効率的・効果的に、現場のニーズにマッチした付加価値の高い人材を育てることが要求されており、そのために人事部主導から各部門・関係会社主導の人材育成体制に転換する必要がある。
では、まず現状の課題と転換に当だっての対応の留意点について述べていきたい。
人事部主導の教育体制の課題
図表1で人事部主導による教育体制の問題を各部門(ライン) と関係会社に分け簡単に整理したが、以下でより掘り下げていく。
(1)各部門(ライン)教育の課題
① 教育は人事部が担当とのことで、各部門は教育について受け身の立場となっており、自部門の教育への問題意識が低いことである。優秀な人材がいないとか、若い人が育たないとかで、他人事のように語る部門長が多々いて、自部門の教育についての役割を認識していない。
②各部門の現場ニーズの声が人事部に届きにくい。例えば、研究開発技術者をどんな人材に、そして、どのようにして育てるのかを、現場部門が技術専門用語を使って説明しても、真意は伝わりにくい場合が多い。また、ライン部門が自部門の育成について危機感を持って、人事部門に説明努力しないことも要因である(人事部は「わかってくれない」との先入観がある)。

