連載 人材と組織の強みを活かすAl 第7回 AI 実践のプロセス ー Destiny
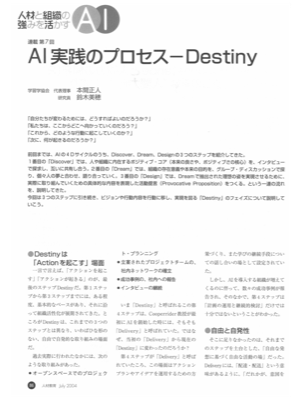
「自分たちが変わるためには、どうすればよいのだろうか?」
「私たちは、ここからどこへ向かっていくのだろう?」
「これから、どのような行動に起こしていくのか?」
「次に、何か起きるのだろうか?」
前回までは、AI の4D サイクルのうち、Discover 、Dream 、Design の3つのステップを紹介してきた。1番目の「Discover 」では、人や組織に内在するポジティブ・コア(本来の良さや、ポジティブさの核心)を、インタビューで探求し、互いに共有し合う。2 番目の「Dream 」では、組織の存在意義や本来の目的を、グループ・ディスカッションで探り、個々人の夢と合わせ、語り合っていく。3番目の「Design 」では、Dream で抽出された理想の姿を実現させるために、実際に取り組んでいくための具体的な内容を表現した活動提言(Provocative Proposition) をつくる。という一連の流れを、説明してきた。今回は3つのステップに引き続き、ビジョンや行動内容を行動に移し、実現を図る「Destiny 」のフェイスについて説明していこう。
Destinyは「Action を起こす」場面
一言で言えば、「アクションを起こす」「アクションが起きる」のが、最後のステップDestiny だ。第1 ステップから第3ステップまでには、ある程度、基本的なベースがあり、それに沿って組織活性化が展開されてきた。ところがDestiny は、これまでの3つのステップとは異なり、いわばひな形のない、自由で自発的な取り組みの場面だ。
過去実際に行われたなかには、次のような取り組みがあった。
●オープンスペースでのプ囗ジェク卜・プランニング
●立案されたプrコジェクトチームの、社内ネットワークの確立
●成功事例の、社内への報告
●インタビューの継続
いま「Destiny 」と呼ばれるこの第4 ステップは、Cooperrider 教授が最初にAI を創始した時には、そもそも「Delivery 」と呼ばれていた。ではなぜ、当初の「Delivery 」から現在の「Destiny 」に変わったのだろうか?第4ステップが「Delivery 」と呼ばれていたころ、この場面はアクションプランやアイデアを運用するための方策づくり、また学びの継続手段についての話し合いの場として設定されていた。
しかし、AI を導入する組織が増えてくるのに伴って、数々の成功事例が報告され、そのなかで、第4ステップは「計画の運用と継続的検討」だけでは十分ではないということがわかった。
自由と自発性
そこに足りなかったのは、それまでのステップを土台とした、「自由な発想に基づく自由な活動の場」だった。Deliveryには、「配達・配送」という意味があるように、「だれかが、意図をもって、あらかじめ定められた目標地点に届ける」という意味が含まれる。しかし、Cooperrider 教授らは、AI の実践を通して実現する変化は長期的なものであり、導入の責任者が「予定通り計画を遂行する」という考え方から離れ、プロジェクトが臨機応変に変化・成長した時に最大の効果を表す、ということに気づいた。

