ケース1 日産自動車 40 億円の成果を達成したV-FAST 推進の要は、ファシリテーターの育成にあり
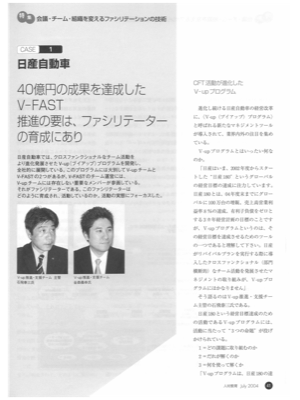
日産自動車では、クロスファンクショナルなチーム活動をより進化発展させたV-up( ブイアップ) プログラムを開発し、全社的に展開している。このプログラムには大別してV-up チームとV-FAST の2 つがあるが、V-FAST のチーム運営には、V-up チームには存在しない重要なメンバーが参画している。それがファシリテーターである。このファシリテーターはどのように育成され、活動しているのか。活動の実態にフォーカスした。
CFT 活動が進化したV-Upプログラム
進化し続ける日産自動車の経営改革に〈V-Up (ブイアップ)プログラム〉と呼ばれる新たなマネジメントツールが導入されて、業界内外の注目を集めている。
V-up プログラムとはいったい何なのか。
「日産はいま、2002 年度からスタートした“日産180 ”というグローバルの経営目標の達成に注力しています。日産180 とは、04 年度末までにグローバルに100 万台の増販、売上高営業利益率8% の達成、有利子負債をゼロとする3ヵ年経営計画の目標のことですが、V-Up プログラムというのは、その経営目標を達成させるためのツールの一つであると理解して下さい。日産がリバイバルプランを実行する際に導入したクロスファンクショナル(部門横断的) なチーム活動を発展させたマネジメントの取り組みが、V-Upプログラムにほかなりません」
そう語るのはV-up 推進・支援チーム主管の石飛泰三氏である。
日産180 という経営目標達成のための活動であるV-Upプログラムには、活動に当たって“3つの命題”が投げかけられている。
1 =どの課題に取り組むのか
2=だれが解くのか
3=何を使って解くか
「V-up プログラムは、日産180 の達成が目標ですので、業績に直結する課題に取り組まなくてはなりません。また課題解決のプロセスでは、部門の壁を超えたクロスファンクショナルなチームが結成され、最も効果的な手法を導入して課題解決することが求められます」(石飛氏)
こうしたV-up プログラムを推進させるアプローチは、大別して次の2つに分かれている(図表)。
V-up チームとV-FAST 。
V-Upチームとは、課題解決の期間が3~ 4ヵ月にわたり、活動に当たって予算計上が必要になるような大型の課題を担当するチームを意味する。一つのチームには部長級の役職者が就任する“Vリーダー”と呼ばれる課題達成責任者と、マネジャー級の役職者から選ばれる“Vパイロットという改善推進担当者が配置される。VリーダーとVパイロットはお互いに共通の達成目標を共有しながら、チーム活動を推進していかなければならない。
さらに、チームには“Vクルー”と呼ばれる6~8名のメンバーがクロスファンクショナルに集められる。

