ケース1 TSネットワーク 「寄せ鍋」活動で 現場での問題整理、解決の方向性を 見出す力を育成
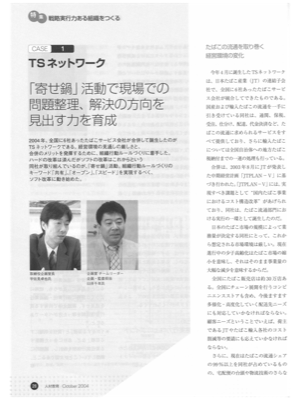
2004 年、全国に6 社あったたばこサービス会社が合併して誕生したのがTS ネットワークである。経営環境の見通しの厳しさと、合併のメリットを発揮するために、組織行動ルールづくりに着手した。ハードの改革は済んだがソフトの改革はこれからという同社が取り組んでいるのが、「寄せ鍋」活動。組織行動ルールづくりのキーワード「共有」、「オープン」、「スピード」を実現するべく、ソフト改革に動き始めた。
たばこの流通を取り巻く経営環境の変化
今年4月に誕生したTS ネットワークは、日本たばこ産業(JT ) の連結子会社で、全国に6社あったたばこサービス会社が統合してできたものである。国産および輸入たばこの流通を一手に引き受けている同社は、通関、保税、受注、仕分け、配達、代金決済など、たばこの流通に求められるサービスをすべて提供しており、さらに輸入たばこについては全国自治体への地方たばこ税納付までの一連の処理も行っている。
合併は、2003 年8月にJT が発表した中期経営計画「JTPLAN - V」に基づき行われた。「JTPLAN - V」には、実現すべき課題としで国内たばこ事業におけるコスト構造改革”があげられており、同社は、たばこ流通部門における実行の一環として誕生したのだ。
日本のたばこ市場の規模によって業務量が決定する同社にとって、これから想定される市場環境は厳しい。現在進行中の少子高齢化はたばこ市場の縮小を意味し、それはそのまま事業量の大幅な減少を意味するからだ。
全国にたばこ販売店は約30 万店ある。全国にチェーン展開を行うコンビニエンスストアも含め、今後ますます多様化・高度化していく配送先ニーズにも対応していかなければならない。顧客ニーズということでいえば、荷主であるJT やたばこ輸入各社のコスト削減等の要請にも応えていかなければならない。
さらに、現在はたばこの流通シェアの99 % 以上を同社が占めているものの、宅配便の台頭や物流技術のさらなる高度化により代替企業が現われないとも隕らない。地球環境に対する意識の高まりから、環境問題へのさらなる対応も迫られる。
こういった経営環境の変化を踏まえたうえで、取締役企画室長の宇佐見卓也氏は、同社の現状の問題点として「コスト構造」と「競争力」の2つをあげた。
「われわれの仕事は、最終的には人の手で行う仕事です。ですから、どうしても人件費の割合は大きくなりますO これは運輸業界に共通する課題ですが、当社の場合は過去の経緯もあり、業界水準に比して割高な賃金水準になっていたことは否定できません。また、分社体制から調達などの非効率性が否めず、合併前はそのスケールメリットを十分に活かし切れていないのが実情でした」
宇佐見氏はコスト構造の問題点について説明したうえで、競争力に関しては次のように語る。
「約30 万店のたばこ販売店に約500弱という銘柄数のたばこを配達している当社は、いわばたばこ流通に特化しか会社です。
たばこ流通の寡占状態を維持できてきたのは、国内最大たばこメーカーであるJT の子会社という特殊性もありますが、他の物流会社にとっては、たばこの流通という特殊な分野に参入するための投資が大きな壁になっているという側面もあると思います。
しかし、競争環境の変化からその壁は着実に低くなろうとしています。競争力の優位性を保つためには、全国レベルでの統一的な戦略・行動の実施の必要性がますます増しているのです」

