人材育成の原点は、「感じる力」を磨くこと

EQとは撈圜の知性。ビジネスで成功した大は、自分自身の感圜の状態を把握し、うまくコントロールするだけでなく、他者の感匱を知覚する能力にも長けているという。組織において「! 里」のみを説いても大は付いて来ない。とりわけ変化のスピードが早い今日、他者への思いやりや感動、センスといった「人の気持ちを感じる力」こそが難局を切り抜けていくうえで大切だという。
私なら「センスのいい人」を採用する
人材を選ぶ時、私なら「センスのいい大」を採用する。配属先だってセンスで決める。そう言うと、「センスつて、いったい何ですか」と、訝しがられたものだ。センスとは、「人の気持ちを感じる力」であると私は考える。念のため辞書を調べてみると、だいたい当たっていた。「物事の微妙な感じを知る心の働き」だそうである。
「そんなあいまいな基準で採用や配属といった重大事を決定していいのか」と、お叱りも受けるが、私は「いいのだ」と言いたい。「IQ 的なものに加え、EQ (Emotional Intelligencがe)不可欠」という一節をある論文のなかで発見した時、私は直感的に「これこそが探していたものだ」という思いに捕らわれた。以後、EQ の意義を世に広め、多くの大に役立ててもらうことが私の仕事になった。
EQ とは日本語でいうセンス、感性、感情といったものに近い。第六感や勘といったものにも似ている。大雑把に括れば「理」に対する「情」である。組織において「理」のみを説いても人は付いて来ない。論理、理論、理性を駆使して戦略を立て、それに基づいて事業を展開していけば成功するかというと、必ずしもそうならない。組織が一丸となって目標に向かって突き進むには、感情と愛情、二つの情のセットがなくてはならない。
特に変化のスピードが速い今日のような時代では、マネジメントのうえで正しい判断をするのが難しくなっている。経験則に基づいて「理」で判断しても、判斷したそばから過去の成功の定石が崩れていくからだ。変化のスピ- ドが「理」の働きよりも速過ぎるのだ。そんな時には、「理」よりも「情」を、センス=感じる力をうまく使うと難局を切り抜けられる。
判断の難しい場面では、「こっちに行くとなんだか危ない気がする」「嫌な予感がする」「気持ち悪い感じがする」といった勘が当たる。これは過去の失敗で痛い思いをした経験が情報として体にインプットされているから、「理」で考えるより先に「情」が働いてストップをかけるのではないか。非科学的に聞こえるかもしれないが、私はこれこそが人間の体の科学だと思っている。
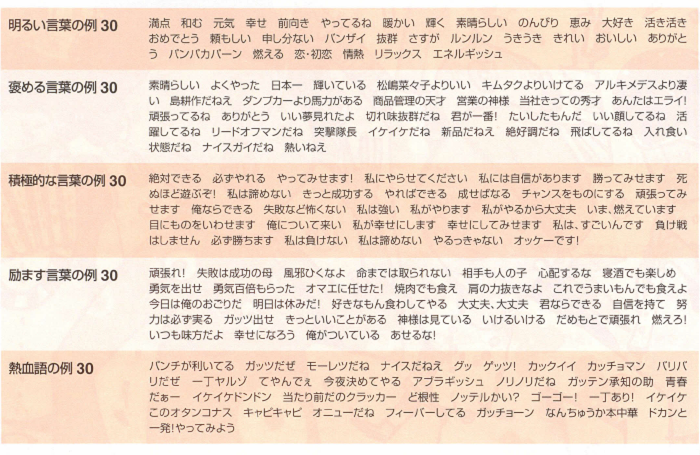
思いやりのスポーツ=野球に学べ
野球の野村克也監督も、センスという言葉をよく使う。「選手を評価する時にはセンスを最優先している」と、何かのインタビューで話していた。記者が「選手のセンスをどこで見分けるのですか」と質問すると、「親を大切にするかどうかだ。それがすべてのプレーに現れる」と答えた。

