新連載 組織の壁を破る! CFT 活動のすすめ 第1 回 CFT 活動は、現状を打破し、 企業の目標を達成する手段
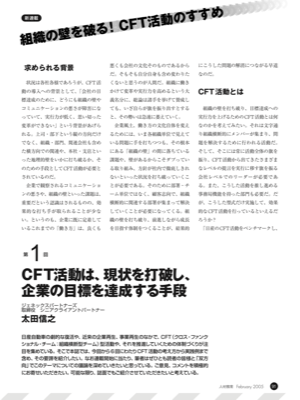
日産自動車の劇的な復活や、近来の企業再生、事業再生のなかで、CFT(クロス・ファンクショナル・チーム:組織横断型チーム)型活動や、それを推進していくための体制づくりが注目を集めている。そこで本誌では、今回から6 回にわたりCFT 活動の考え方から実践例まで含め、その要諦を紹介したい。なお連載開始に当たり、筆者はぜひとも読者の皆様と「双方向」でこのテーマについての議論を深めていきたいと思っている。ご意見、コメントを積極的にお寄せいただきたい。可能な限り、誌面でもご紹介させていただきたいと考えている。
求められる背景
状況は各社各様であろうが、CFT活動の導入への背景として、「会社の目標達成のために、どうにも組織の壁やコミュニケーションの悪さが障害になっていて、実行力が低く、思い切った変革ができない」という背景があげられる。上司・部下という縦の方向だけでなく、組織・部門、関連会社も含めた横方向での関連や、本社・支店といった地理的壁をいかに打ち破るか、そのための手段としてCFT活動が必要とされているのだ。
企業で観察されるコミュニケーションの悪さや、組織の壁といった課題は、重要だという認識はされるものの、効果的な打ち手が取られることが少ない。というのも、企業に既に定着しているこれまでの「働き方」は、良くも悪くも会社の文化そのものであるからだ。そもそも自分自身も含め変わりたくないと思うのが人間だ。組織に働きかけて変革や実行力を高めるという大義名分に、総論は諸手を挙げて賛成しても、いざ自らが旗を振り出すとすると、その勢いは急速に萎えていく。
企業風土、働き方の文化自体を変えるためには、いま各組織単位で見えている問題に手を打ちつつも、その根本にある「組織の壁」の間に落ちている課題や、壁があるからこそダブっている取り組み、方針が社内で徹底しきれないといった状況を打ち破っていくことが必要である。そのために部署・チーム単位ではなく、顧客志向で、組織横断的に関連する部署が集まって解決していくことが必要になってくる。組織の壁を打ち破り、前進しながら成長を目指す体制をつくることが、結果的にこうした問題の解消につながる早道なのだ。
CFT 活動とは
組織の壁を打ち破り、目標達成への実行力を上げるためのCFT活動とは何なのかを考えてみたい。それは文字通り組織横断的にメンバーが集まり、問題を解決するために行われる活動だ。そして、そこには常に活動全体の旗を振り、CFT活動から出てきたさまざまなレベルの提言を実行に移す旗を振る会社レベルでのリーダーが必要である。また、こうした活動を推し進める事務局機能を持った部門も必要だ。だが、こうした型式だけ実施して、効果的なCFT活動を行っているといえるだろうか?
「日産のCFT活動をベンチマークし、コスト削減5 %を達成しました」と自慢げに語る製造業の役員の方とお話ししたことがある。聞けば、メンバーはボランティアで集められ、目標はメンバーの判断で決められ、提言に対してのコミットメントを求めるような体制や機能も特段整備されていないという。こうした状況での5 %のコスト削減は立派である。しかし、お話を伺うだけで、「本当はもっと効果が上がったのではないだろうか」「むしろコスト削減からのリスクだけを増やしてしまったのではないだろうか」「計画としては5 %かもしれないが、結局実行には移せないのではないだろうか」とさまざまな疑念が頭をよぎった。
断言できるが、CFT活動で成果を上げている企業をベンチマークして研究することは役には立つが、形をそのまま自社に導入するだけでは全く意味がない。

