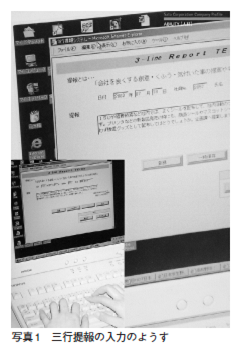人事制度解体新書 第21 回 サトー 「三行提報」で全社的な ナレッジマネジメントを実現。 さらに年俸制を一般社員まで拡大

サトーの人材育成の根底にあるのが、創業以来続いている社員とトップを結ぶ独自のコミュニケーションツール「三行提報」だ。会社を良くする創意・工夫、気づいたことの提案や考えとその対策の報告などを三行以内で毎日行う制度で、それによりさまざまな人事施策が実行に移されている。また、本年4月からは全社員年俸制へと移行、成果主義に対する認識を全社に浸透させることにも成功した。「三行提報」と「年俸制」を担当する責任者に、詳しい話を伺った。
「三行提報」の持つ大きな意味
1976年からサトーのユニークな制度として「三行提報(以下、提報)」がある。単なる日報ではなく、創意工夫や自分の考えを盛り込んだ形で、三行に文章でまとめて提出していく制度だ。海外を含め、全社員が全営業日に提出しなければならない。
「現在、1,400人近くの社員から毎日、この提報が届けられています。提案の内容は、営業活動のなかで気づいたことや市場の動向、職場の改善案、製品の使い勝手や工夫点、などさまざまです。宛て先が会長・社長なので、ダイレクトに提案されるトップとの“ホットライン”のツールですね」と語るのは、経営企画本部総務部ナレッジマネジメントグループ・グループ長の野木りえ子氏である。
情報が双方向なのも大きな特徴だ。トップが見て、その情報に対する“重みづけ”を行い、点数を付しているのである。そして、その点数をフィードバックし、時にはコメントが付いてくる。さらに提報の内容に関連する担当責任者へは、改善の指示が伝えられる。毎日行われるので、要望や市場の変化に合わせた形で、速やかな対応が必然的に行われていく。
「トップから指示が出たものに関しては、スピーディーに取り掛かることになっています。さらに、この問題についてトップが詳細を聞きたいという場合には、詳しい報告をしなければなりません。レスポンスをすぐに出すことが大命題であり、これが提報の持つ大きな意味です」(野木氏)
トップに上げる提案は1日50件程度にスクリーニングする。ただ、それ以外の提案も、担当部署レベルで役立つものが少なくない。そこで、当該の部署からも、「評価点」が付く仕組みとなっている。
毎日提出でビジネススキルや感性が磨かれていく
提報は会社の“経営のサポート的役割”を担っている。また個人に対しては、人事考課や報酬制度などに関連する。毎日提出が100 %義務付けられていることから、大変さが伺える。もし果たせなかった場合、個人の評価だけに留まらず、チームにも影響を及ぼすという。連帯責任が求められているわけだ。例えば、報酬の一環として「月次表彰」が行われているが、提報の情報の重みによってポイントが付されており、その合計で毎月、個人とチームの双方に対する表彰が行われる。これでは気が抜けない。
また、トップからの指示と担当者が独自に取り組んだテーマで、それが改善まで結びついたものに対しては、年間表彰する。これも改善した部門と個人が表彰される仕組みとなっている。
こうして獲得された点数を半年、あるいは1年ごとに集計して、人事考課や優秀社員選出の基本データとしている。さらに、賞与とは別に、提報の獲得ポイントに対しての「加算金」が加わる。さまざまなシステムが有機的に絡み、「全員が徹底して取り組まなければならないもの」となっている。
「事実、提報の提出率は99%に達しています。100 %に足りなかった部分も、うっかり出し忘れたといった類のもので、まさに社内文化として定着しています」(野木氏)
76年にスタートした当初は、「企業日報」という形で始まった。従業員数が増えていくに従い、全員の日報をきちんと見るためにはある程度の“コンパクトさ”が必要ということで、三行(127 文字)というサイズに収斂していった。
「三行/127文字」という制限があるなか、具体的な名称や提案先を必ず盛り込まなければならないルールがある。そして毎日書くことで、何か提報に書くネタはないかと皆が常にアンテナを張ることとなり、それがビジネス的な感覚を磨く効果を生み出していく。さらに文章能力や要約力の向上にもつながる。まさに提報を通して、さまざまなビジネススキルや感性が鍛えられていくのだ。たかが三行、されど三行である。
ウェブ化でナレッジマネジメントの機能が増した

「2年前、提報が社内ウェブ化されました。これ以降、全社員の提報が社内データベースとして載ることとなり、さまざまなキーワードでの検索などが可能となりました。例えば、自分の担当する部署をキーワードとして入れると、他の社員からどういう意見や要望があるかということが、一目でわかるようになっています。新製品やシステムをつくる際の“情報の宝庫”と化していったのです。また、個人名でも検索でき、さまざまな場面での活用が可能です。ナレッジマネジメント機能が、一気にパワーアップしたと言えます」(野木氏)
“中間”で情報が滞留することがなく、ダイレクトにトップに情報が入る。情報が速やかに上がることが重要なポイントで、海外であっても同様だ。海外で昨日起こったことが、今日には全員が知ることができる。
「分類のなかに、商談事例というカテゴリーが設けられていますが、ある地域で成功した事例を他の地域でも参考にして応用する動きが出ています。リアリティーのある情報を皆が共有することで、新たな情報の展開が生まれているのです」(野木氏)
こうしたウェブによる「横展開」の持つダイナミズムは、それこそ話題の「電車男」の世界のようにも感じた。
「トップに上がったものだけでなく、全員の情報が載ることで、ある人の提報に対して、多くの人が意見を言えるようになったのです。それも、必ずしも担当部署からのものではなく、そのことを知っている人が教えていくといった形で、広くあまねく情報交換が行われるようになりました」(野木氏)
経営に物申す「権利」としてのツール