新連載 実践シャドーコーチング 第1回 「シャドーコーチング」とは何か?

いま、コミュニケーションの必要性が高まっているのにもかかわらず、上司・部下間でのコミュニケーション不全が職場での大きな問題となっています。これはなぜでしょう? 思うに、上司であるあなたの「伝え方」が間違っている、あるいは一方的過ぎることに原因があるのではないでしょうか。というのは、職場の風通しや雰囲気をつくり出す感情の流れには法則があり、風上にいるのは常に上司で、そこから風下にいる部下たちへと感情は伝染するのです。では、あなたが自信を持って、適切な「表情」「表現」で部下へと語りかけていき、理解と共感を促すコミュニケーションをしていくにはどうしたらいいのでしょう……。本連載では、読者モデル(管理職)に登場してもらい、EQ 検査による事前アセスメント(行動特性把握)を行うとともに、コーチである私と一緒に日々の行動をチェックしながら、より良い行動を目指していく「シャドーコーチング」を実施していきます。また、ライブ感あふれる誌面構成を掲載しながら、シャドーコーチングの一つのやり方を紹介する仕掛けにしていきます。まずは第1回目、なぜいまシャドーコーチングなのか? という話から進めてみましょう!
「コーチング」がなぜ職場に根づかないのか?
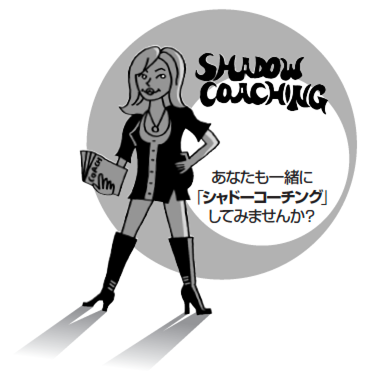
職場のコミュニケーション不全に対する一つの策として、新たなコミュニケーションスタイルを取り入れるためにコーチング研修を受けたことのある管理職は多いはずである。しかし、その管理職が戻る職場では、部下から良い行動を引き出す働きかけが必ずしもできず、コーチング・アプローチのコミュニケーションが機能していない現状が同時にある。これは、なぜか?
コーチングを適切に機能させるには、コーチングを行うために必須となる「コミュニケーション・スキル」と、「コーチとして相手に向き合う際のスタンス(こころ構え)」という二つの側面を学ぶ必要がある。しかし現状では、企業研修には時間的制約もあり、どうしても「スキル」偏向になっているのではないだろうか。
私は、コーチングが適切に機能するかどうかは、コーチのスタンスで決まると考える。たとえコーチングのスキル力が多少おぼつかなくても、相手と接するコーチのこころの姿勢が真っ直ぐであれば、必ずお互いが良い方向に振れていくものだ。人は、感情で動く。本来、人にはEQ という能力があり、相手の感情を敏感に感じとれるはずだ。
しかし、もしコーチ(上司)が、相手(部下)の視点に立たず、また相手の成長や目標達成をこころから願わずに、研修で教えられた通りの質問スキルだけ使ったなら、部下は上司の下心やウソを見抜き、結果的に警戒心や嫌悪感を生じさせるだけになるのだ。
一方で、コーチ(上司)のスタンスは真摯であるのに機能しないことがある。それは、コーチ(上司)自身が、慣れないことをしてギクシャクしている自分に不安になり、本当に使えるようになる前にやめてしまうからだろう。
コミュニケーション・スキルは、場数を経て身につくものである。身体の筋肉痛と同じく、慣れない対人アプローチをしようとするとこころが筋肉痛を起こす。しかし、この辛さは、こころ(EQ)の一部が鍛えられている際のサインであり、それを越えればこころに弾力がつきスキル発揮が容易になることを信じてほしい。
「コーチング」にも“落とし穴”がある
コーチングに意外な“落とし穴”があることをご存知だろうか?
通常のコーチングは、コーチとクライアントの二人っきりの空間(電話コーチングも含む)にて行われる。クライアントはコーチングを受けて、自ら日々の行動目標を設定し、後日その結果をコーチとシェアして振り返り、必要に応じてコーチからフィードバックを受けるという一連の流れがあるわけだが、そのプロセスにおいて、本人の「勘違い」が意外にあったりする。
なぜなら、本人が認識していない日々の行動のクセ、考え方のパターンというものがあるからだ。人間には後ろに目があるわけではない。自分では「ちゃんとやっている」と思っていても、それが適切かつ効果的に行われているかを「確認する術」はないのだ。また、後日コーチに日頃の「成果」の報告をする場合でも、あくまでそれは自己申告でしかない。それが本当かどうかは、実はわからないというのが正直なところである。
誤解ないように言うが、コーチはクライアントを信じている。しかし、特に私が行うコーチングのテーマはEQがかかわる領域であり、自分および他者の感情マネジメントやコミュニケーション・スキルが焦点となるため、クライアントに適切なやり方の知識があり、なおかつ「適切に実践しているか」を正確に把握することが重要なポイントになる場合がある。
通常のコーチングは、「何を行うか」(=WHAT)を決める時間ともいえる。「いかに行っているか」(= HOW)の実地検証はコーチングの範囲外にある。そこで、実際の現場でコーチングを行うという「シャドーコーチング」の有効性が高まってきたというわけである。シャドーコーチングは、管理職がコーチング研修で学んだスキルを職場活用するための、現場サポートの仕組みとしても応用可能であろう。
シャドーコーチングの目的
シャドーコーチングは、アメリカでは90年代後半から活用されているコーチングの一種で、コーチがクライアントの様子を1 日または半日程度影のように同行して観察し、その場で気づいたことをフィードバックやサジェストしたり、後ほど客観的視点からレポートしたりするものである。特に、エグゼクティブクラスでの活用が盛んのようだ。つまり、お気づきかもしれないが、スポーツにおけるコーチそのものの形、その職場版である。スポーツにおける技術鍛錬と同様に、職場版のシャドーコーチングでは、コミュニケーションスキル向上などの技術鍛錬が主な目的となる。
日本では、まだまだその認知度合いは低く、私のコーチング仲間でも、シャドーコーチングの存在を知らない人は多い。事実、インターネットで検索しても、日本語のサイトではほとんど引っかかることはなかった。
日本でシャドーコーチングが広まらない理由としては、そもそも養成されたコーチの数がまだ少ないことがあげられるが、そのほかに、シャドーコーチングはクライアントと行動をともにするという特性があるゆえに、見ず知らずの第三者が職場内を歩き、会議にも同席することに対して、企業内では受け入れられにくい「心理的な壁」が存在するからではないだろうか。学校での授業参観のごとく、簡単にはいかないのである。
その意味でも、これからはコーチ自身もシャドーコーチングの価値や重要性をアピールしていき、「心理的な壁」を取り払い、社内でも受け入れられるような素地をつくっていくことが求められる。いずれにしても、シャドーコーチングでは「現場」を押さえることができるのが最大の強み。これを生かさない手はないと思う。
シャドーコーチングの進め方
では、職場内でシャドーコーチングを実際に進めていくステップについて、ここではEQ アセスメントを併用しながらの方法をご紹介したい。
(1)コーチングに際して、まず周囲の人たちにクライアント(シャドーコーチングの対象となる人)の印象や評判、評価などを聞き、それをクライアント本人にフィードバックする。「360度評価」のような視点が盛り込まれる。もちろん、周囲の人たちには、名前は特定しないので本人に話の内容を伝えたいと許可を得る必要がある。
(2)他方で、EQ アセスメントを使って、クライアント自身が思う自分自身の行動発揮状態を数値として映し出し、客観的かつ視覚的に自分自身を把握する。その結果を切り口にして、コーチは、現在の行動をつくり出しているクライアントの感情の持ち方、考え方、価値観などについて、コーチングしていく(掘り下げて浮き彫りにしていく)。

