連載 人事制度改革はなぜ失敗するのか 第3 回 経営の流れを見失った 人事制度改革の失敗
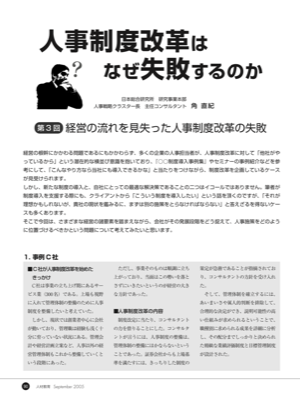
経営の根幹にかかわる問題であるにもかかわらず、多くの企業の人事担当者が、人事制度改革に対して「他社がやっているから」という潜在的な横並び意識を抱いており、『○○制度導入事例集』やセミナーの事例紹介などを参考にして、「こんなやり方なら当社にも導入できるかな」と当たりをつけながら、制度改革を企画しているケースが見受けられます。しかし、新たな制度の導入と、自社にとっての最適な解決策であることの二つはイコールではありません。筆者が制度導入を支援する際にも、クライアントから「こういう制度を導入したい」という話を頂くのですが、「それが理想かもしれないが、貴社の現状を鑑みるに、まずは別の施策をとらなければならない」と答えざるを得ないケースも多くあります。そこで今回は、さまざまな経営の諸要素を踏まえながら、会社がその発展段階をどう捉えて、人事施策をどのように位置づけるべきかという問題について考えてみたいと思います。
1. 事例C 社
C社が人事制度改革を始めたきっかけ
C社は事業の立ち上げ期にあるサービス業(300 名)である。上場も視野に入れて管理体制の整備のために人事制度を整備したいと考えていた。
しかし、現状では創業者中心に会社が動いており、管理職は経験も浅く十分に育っていない状況にある。管理会計や経営計画立案など、人事以外の経営管理体制もこれから整備していくという段階にあった。
ただし、事業そのものは順調に立ち上がっており、当面はこの勢いを落とさずにいきたいというのが経営の大きな方針であった。
人事制度改革の内容
制度改定に当たり、コンサルタントの力を借りることにした。コンサルタントが言うには、人事制度の整備は、管理体制の整備にほかならないということであった。証券会社からも上場基準を満たすには、きっちりした制度の策定が急務であることが指摘されており、コンサルタントの方針を受け入れた。
そして、管理体制を確立するには、あいまいさや属人的判断を排除して、合理的な決定ができ、説明可能性の高い仕組みが求められるということで、職種別に求められる成果を詳細に分析し、その配分までしっかりと決められた精緻な業績評価制度と目標管理制度が設計された。
改革の結果
制度導入時に1日かけて評価者研修を実施したものの、結果として評価制度はうまく機能しなかった。ネックになったのは評価者であった。形こそ整っているが、部下が納得する説明ができないため、社員から不満の声が上がってきたのである。
さらに、人事部が説明したにもかかわらず、トップが最終評価段階で一次・二次評価の積み上げを無視して「これはおかしい」と最終評点を変更してしまう事態が起こってしまった。フィードバックしようにもできない状況になってしまったのである。
これに対してトップへの批判もささやかれたが、主因はむしろ上司である管理職にあった。というのも、管理職はフィードバックしやすいようにと厳しい評価を付けるのを避け、明らかに甘い評価を下していたのであった。
時間がたつに従って、社内では処遇面での厳しさだけが浮き彫りにされ、新人事制度への不満が高まってきた。一方で、これまでは自分の考えをストレートに査定で示していたトップも、新制度ではなかなかその思いが届かない感覚を持ち、満足はしていなかった。
最終的には、新しい評価用紙は使われなくなり、これとは別に、事実上、従来通りの査定が行われることになってしまった。そのことが漏れ伝わり、管理職に対するスタッフの不信感、あるいはトップへの不満が組織内で大きくなり、事業の勢いを落としかねない事態に陥ってしまった。
2. なぜ改革は失敗したのか
C 社の置かれていた状況
C社は企業のライフサイクルでいうと、事業立ち上げ期から成長期に差し掛かった辺りにポジションしていると考えられます。

