CASE1 アクサ生命保険 アクションラーニングで 行動変革とCS 向上を実現
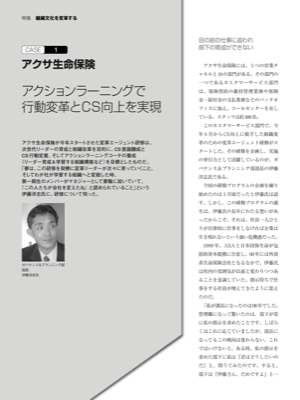
アクサ生命保険が今年スタートさせた変革エージェント研修は、次世代リーダーの育成と組織改革を目的に、CS 意識醸成とCS 行動定着、そしてアクションラーニングコーチの養成(リーダー育成&学習する組織構築など)を目標としたものだ。「夢は、この研修を契機に変革リーダーが次々に育っていくこと。そしてわが社が学習する組織へと変貌した時、第一期生のメンバーがマネジャーとして要職に就いていて、『この人たちが会社を変えたね』と認められていること」という伊藤洋志氏に、研修について伺った。
目の前の仕事に追われ部下の育成ができない
アクサ生命保険には、5つの営業チャネルと10の部門がある。その部門の一つであるカスタマーサービス部門は、保険契約の維持管理業務や保険金・給付金の支払業務などのバックオフィスに加え、コールセンターを有している。スタッフは約400名。
このカスタマーサービス部門で、今年6月からCS 向上に根ざした組織変革のための変革エージェント研修がスタートした。その研修を企画し、実施の牽引力として活躍しているのが、ガバナンス&プランニング部部長の伊藤洋志氏である。
今回の研修プログラムの企画を練り始めたのは3月頃だったと伊藤氏は話す。しかし、この研修プログラムの誕生は、伊藤氏の長年にわたる想いがあったからこそ。それは、社員一人ひとりが自律的に仕事をしなければ企業は生き残れないという強い危機感だった。
1999 年、AXA と日本団体生命が包括的資本提携に合意し、00年には外資系生命保険会社となるなかで、伊藤氏は社内の雰囲気が以前と変わりつつあることを意識していた。指示待ちで仕事をする社員が増えてきたように思えたのだ。
「私が課長になったのは98年でした。管理職になって驚いたのは、部下が常に私の指示を求めたことです。しばらくはこれに応じていましたが、部長になってもこの傾向は変わらない。これではいけないと、ある時、私の指示を求めた部下に私は『君はどうしたいのだ』と、問うてみたのです。すると、部下は『伊藤さん、だめですよ』と一言。まるで上司失格と言わんばかりでした」と、伊藤氏は振り返った。
「指示待ち型が増えたのは、スタッフの育成ができていないことにも原因があると思いました。外資系企業となり、マネジャーもほとんどがプレイングマネジャー。部下の育成に力を注ぐことよりも、現場リーダーとして目の前の仕事に忙殺されるというのが現状です。その結果、スタッフが育たず、自律的に仕事する訓練ができていなかったのだ思います」と、伊藤氏は分析した。
学習する組織というキーワードが盛んに用いられるようになったのも、この頃だ。
組織自体に変化し続ける能力がなければ、加速する経営環境の変化に応じて顧客のニーズを察知し、そのうえで顧客が求める商品を提供することなど不可能であり、激しい企業間競争のなかで生き残ることはできない。学習する組織、いわば変化し続ける企業であるためには、自律型社員を育成しなければならない。
同社の課題はほかにもあった。CS(顧客満足度)が必ずしも高くないことに加え、複数のES(従業員満足度)調査も、いずれもよくないという結果が出ていたからだ。
もちろん、こういった課題にアクサ生命保険は、真摯に取り組んできていた。
CS 向上のために全社レベルの活動として内外顧客の声を経営に活かすためのワーキンググループ活動を実施し、部門レベルでもCS 向上を促す研修を実施した。ES向上に対しては、職場改善に繋がる部門研修を実施、各部レベルでのES向上も目指した。学習する組織の構築については、部門内階層別研修を実施し、定例マネジャーミーティングではワークショップも行った。
しかし、伊藤氏は思い悩んでいた。CS やES の向上にしろ学習する組織の構築にしろ、課題の本質を解決する手法をつかんでいなかったからである。
そんな時、伊藤氏が出会ったのが、アクションラーニングの手法だった。
アクションラーニングは、チームで、現実に起こっている具体的な課題をさまざまな視点から検討し、解決策を立てアクションへと展開し、その試行錯誤の問題解決プロセスそのものから学ぶという手法である。具体的には、そのプロセスを振り返り、検証することで、個人および組織として成功パターンを学習していくというもの。この手法は30年代に開発され、欧米の企業などでは最も注目されている手法であり、コーポレートユニバーシティなどでは定番になっている。
伊藤氏は、アクションラーニングの基礎講座を学び、さらには、アクションラーニングコーチの養成講座にも通い、06 年3 月にはコーチの認定を受けていた。
アイデアが出ないのはCS意識が希薄だから
アクションラーニングの手法を用いれば、これまでバラバラに取り組んでいた、CS、ES の向上と学習する組織の構築をともに実現できる研修プログラムをつくることができるはずだ。その結果、組織変革も実現できるのではないかと、伊藤氏は考えたのである。
CS とES は密接な関係があることから、伊藤氏は、まずは意識醸成の土壌を耕すような研修の必要性を感じた。そこで05年9月から半年かけて実施したのが「Fish! 研修」だった。

