連載 HR Global Eyes 世界の人事 ニッポンの人事 Vol.4 中途採用の仕組みは 欧州に学べ
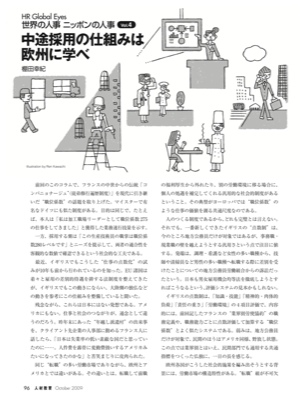
前回のこのコラムで、フランスの中世からの伝統「コンパニョナージュ”(徒弟修行遍歴制度)」を現代に引き継いだ“職位係数”の話題を取り上げた。マイスターで有名なドイツにも似た制度がある。目的は同じで、たとえば、本人は「私は加工職場リーダーとして職位係数275の仕事をしてきました」と獲得した業務遂行技量を示す。
一方、採用する側は「この生産技術員の職掌は職位係数280レベルです」とニーズを提示して、両者の適合性を客観的な数値で確認できるという社会的な工夫である。
最近、イギリスでもこうした“仕事の点数化”の試みが10年も前から行われているのを知った。EU 諸国は着々と雇用の差別的待遇を排する法制度を整えてきたが、イギリスでもこの動きにならい、大陸側の独仏などの動きを参考にこの仕組みを整備していると聞いた。
残念ながら、これらは日本にはない発想である。アメリカにもない。仕事と社会のつながりが、通念として違うのだろう。昨年末にあった“年越し派遣村”の出来事を、クライアント先企業の人事部に勤めるフランス人に話したら、「日本は失業率の低い素敵な国だと思っていたのに……。人件費を露骨に変動費扱いするアメリカみたいになってきたのかな」と苦笑まじりに皮肉られた。
同じ“転職”の多い労働市場でありながら、欧州とアメリカとでは違いがある。その違いとは、転職して前職の福利厚生から外れたり、別の労働環境に移る場合に、個人の処遇を補完してくれる汎用的な社会的制度があるということ。その典型がヨーロッパでは“職位係数”のような仕事の価値を測る共通尺度なのである。

