OPINION1 研修とeラーニングの担当者は協働を ブレンド型教育体系 構築のススメ
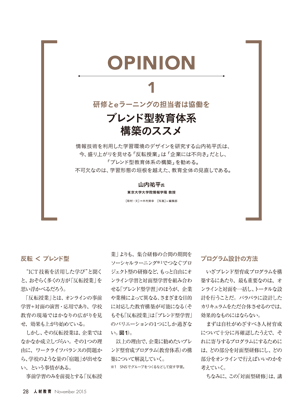
情報技術を利用した学習環境のデザインを研究する山内祐平氏は、今、盛り上がりを見せる「反転授業」は「企業には不向き」だとし、「ブレンド型教育体系の構築」を勧める。
不可欠なのは、学習形態の垣根を越えた、教育全体の見直しである。
反転 < ブレンド型
“ICT 技術を活用した学び”と聞くと、おそらく多くの方が「反転授業」を思い浮かべるだろう。
「反転授業」とは、オンラインの事前学習+対面の演習・応用であり、学校教育の現場ではかなりの広がりを見せ、効果も上がり始めている。
しかし、その反転授業は、企業ではなかなか成立しづらい。その1つの理由に、ワークライフバランスの問題から、学校のような量の「宿題」が出せない、という事情がある。
事前学習のみを前提とする「反転授業」よりも、集合研修の合間の期間をソーシャルラーニング※1でつなぐプロジェクト型の研修など、もっと自由にオンライン学習と対面型学習を組み合わせる「ブレンド型学習」のほうが、企業や業種によって異なる、さまざまな目的に対応した教育構築が可能になる(そもそも「反転授業」は「ブレンド型学習」のバリエーションの1つにしか過ぎない。図1)。
以上の理由で、企業に勧めたいブレンド型育成プログラム(教育体系)の構築について解説していく。
※1 SNSでグループをつくるなどして促す学習。
プログラム設計の方法
いざブレンド型育成プログラムを構築するにあたり、最も重要なのは、オンラインと対面を一括し、トータルな設計を行うことだ。バラバラに設計したカリキュラムをただ合体させるのでは、効果的なものにはならない。
まずは自社がめざすべき人材育成について十分に再確認したうえで、それに寄与するプログラムにするためには、どの部分を対面型研修にし、どの部分をオンラインで行えばいいのかを考えていく。
ちなみに、この「対面型研修」は、講義型の集合研修のみにとどまらず、「オンライン学習」もeラーニングにとどまらない。

