OPINION 2 社会人の“学び直し”の場へ MOOCは企業内教育をどう変えるか
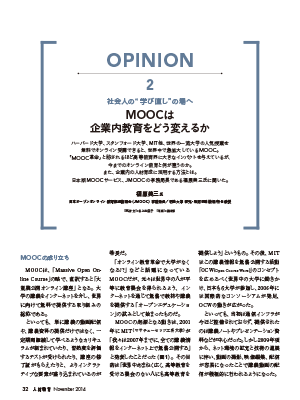
MOOCの成り立ち
MOOCは、「Massive Open OnlineCourse」の略で、直訳すると「大規模公開オンライン講座」となる。大学の講義をインターネットを介し、世界に向けて無料で提供する取り組みの総称である。
といっても、単に講義の動画配信や、講義資料の提供だけではなく、一定期間継続して学べるようなカリキュラムが組まれていたり、習熟度を評価するテストが受けられたり、講座の修了証がもらえたりと、よりインタラクティブな要素が盛り込まれているのが特長だ。
「オンライン教育革命で大学がなくなる! ?」などと話題になっているMOOCだが、元々は世界中の人が平等に教育機会を得られるよう、インターネットを通じて無償で教材や講義を提供する「オープンエデュケーション」の試みとして始まったものだ。
MOOCの起源となる動きは、2001年にMIT(マサチューセッツ工科大学)が「我々は2007年までに、全ての講義情報をインターネット上で無償公開する」と発表したことだった(図1)。その目的は「世界中あまねく広く、高等教育を受ける機会のない人にも高等教育を提供しよう」というもの。その後、MITはこの講義情報を無償公開する活動「OCW(Open Course Ware)」のコンセプトを広めるべく世界中の大学に働きかけ、日本も6大学が参加し、2006 年には国際的なコンソーシアムが発足、OCWの動きが広がった。
といっても、当初は通信インフラが今ほど整備されておらず、提供されたのは講義ノートやプレゼンテーション資料などが中心だった。しかし2009年頃から、ネット環境の拡充と技術の進展に伴い、動画の撮影、映像編集、配信が容易になったことで講義動画の配信が積極的に行われるようになった。
その後、コンテンツが増え、学習者数が拡大するにつれ、学習者のモチベーションを高めるために、獲得した知識やスキルを認定する資格認定を行う動きや、教員から学習指導を受けられない代わりに、学習者同士が参加できるオンラインコミュニティーを用意して学び合いを支援する、などの動きが出てきた。
こうした仕組みを取り込んだ学習プラットフォームとして、2012 年に「Coursera」や「edX」「Udacity」「FutureLearn」といったサイトが相次ぎ登場した。これらのサイトからは学費の高い超一流大学の講座が受講でき、しかも修了証を得ることもできるとあって、受講者数は急増。現在、世界中で1500万人以上が受講している。
MOOCへの講座提供が国際的に優秀な学生の発掘、獲得につながる動きもあり、大学側も乗り遅れまいと相次いで参加を表明。日本の大学も、東京大学はCourseraとedXへ、京都大学はedXへ英語による無料講義を配信している。
MOOCの特長
MOOCがわずか2年ほどの間に、爆発的に拡大したのはなぜだろうか。その理由は、これまでのオンライン教材、オンライン講座になかったようないくつかの特長を備えているところにある。ここで、MOOCの8つの特長を解説したい。
①無償提供

