連載 人事制度解体新書 【第7回】 パタゴニア 社員の「人生全体」を充実させることで、 働く意欲を引き出すことに成功

社員の「成果」や「実績」を問うためには、それを担保する個人の選択の「自由」が必要だ。とはいうものの、これが現実的には難しいのが経営・人事サイドの悩みではないだろうか。そんななかで、米国アウトドアウェアメーカー・パタゴニア日本支社では、「社員の満足なしに顧客の満足は実現できない」という考えの下、社員の私生活の充実を積極的にサポートしている。その結果、充実した私生活を送らせてくれる会社に対する強いロイヤルティーが生まれ、結果、社員全体にモチベーション向上が図られているという。いったい、どんな「私生活充実」方法が効果があるのか、日本支社の責任者に、話を伺った。
「クオリティ・オブ・ライフ」を保障する理由
現在では、いかなるウェアにおいても妥協のない製品作りを誇るパタゴニアだが、その始まりは、高校を卒業したばかりの「タードバッグ(熱心なアウトドア愛好家)] イヴォン・シユイナードが、粗末なブリキ小屋から創業した1957 年のことである。そして、半世紀近くを経た現在では、3つの棟から成る本社を構えるに至った。しかし創業来の社員の仕事とアウトドアに対する意識は変わらない。なんと仕事の合間でも、良い波が来ていると聞けばビーチに駆け出す一方、会議の合間を利用してはバイク乗りに夢中になる輩ばかりである。
ちょっと日本では考えられないような「光景」だが、こうした社員の私生活、自由を尊重する姿勢のバックボーンにあるのは、「パタゴニアでは、製品のクオリティーを高く維持するためには、社員の生活(クオリティー・オブ・ライフ)も同様に高いレベルで保障されていなければならない、という考えが根づいているからです」と語ってくれたのが、ファイナンシャル・コントローラーの坪内秀三氏である。
こうした「パタゴニア・スピリット」が日本にもたらされたのは、日本支社が設立された1988年のこと。翌年、東京・目白に日本初の直営店がオープン。そして94 年に鎌倉が2号店としてオープンする前年の93 年、社員側の多数が要望したということもあって、鎌倉が日本支社の地となった。なぜ鎌倉なのかは、賢明な読者のこと、改めて言わなくてもおわかりだろう(付け加えると、取材当日の朝、サーフボードを小脇に抱えて出勤するスタッフを目の当たりにした)。
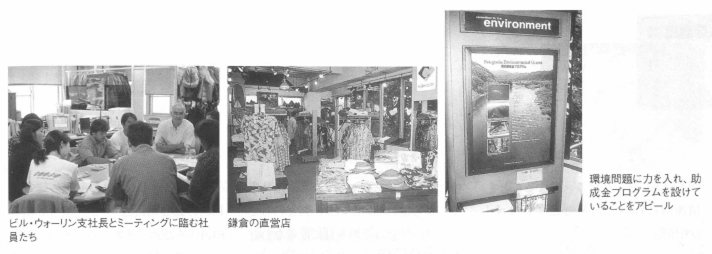
「会社」と「個人」 お互いがハッピーな関係
ところで近年、日本経済に活気がないことのなかに、何よりも働く従業員が元気のなさがあるのではないだろうか。リストラの結果、これまでより少ない人数で仕事をこなさなければならなくなった。ましてや残業時間は増えても「成果主義」だから、それがなかなか「報酬」へと結び付かない。
その結果、心身ともに閉塞感に蝕まれる、といった悪循環が生じているケースが少なくない。ゆえに、近年のHRM (ヒューマン・リソース・マネジメント)の一方向として、「モチベーション」をどう図るかが、非常に注目されているのである。パタゴニア日本支社に取材させてもらった理由も、「人」をワクワクさせ、「能力」を生かす組織をいかにつくっていくか、を聞くためにほかならない。
「当社が160 名という社員規模で、かつアウトドアを業としているから可能かもしれませんが」と断ったうえで、坪内氏は「会社」と「個人」の関係のあり様について、語り始めた。
「最近、会社を通して学ぶ、経験を重ねるということが言われますが、一般的に、それはなかなか難しいように思います。まず、組織であるがゆえにさまざまな『ルール』というものが存在します。そして、それは『公平』でなくてはなりません。ただそのルールを全面に押し出していくと、言いたいことも言えなくなってしまいます。だから、活力を生むためには、“掟破り”を認める『柔軟性』が必要です。しかし、その“さじ加減”がとても難しい。実際問題、ルールが前提にあったとしても、現実にはルールでは表現できないケースに常に遭遇しますから。まさにその時、どう対処していけるかが大きなポイントとなりますね」
「その通り」だと思った。プライベートなことや家庭生活で問題が生じた際、だれでもこうした状況での対処如何で、モチベーションのあり様が大きく左右されるのは人の常だからだ。その時に、ルール一辺倒では解決にならない。かといって、個人の都合を優先ばかりをしていては、それはそれで問題だ。ルールを尊重しつつも、そのなかで「会社」と「個人」がお互いに八ッピーとなれるような状態をつくり出していけるか、ここがとても重要だ。
「例えば、遠隔地から通勤する社員が、自ら住居を勤務地の近くに引っ越す場合、そのための引っ越し費用を会社が負担することがあってもいいと思います。なぜなら、もし遠隔地から通勤する場合には会社が負担する交通費が相当額かかるわけです。その分を引っ越し費用が相殺していると考えればいいのではないでしょうか。こうした会社と働く個人の両者の都合を両立させていくためには、『就業規則』などはできるだけシンプルにして、会社と個人双方にとってプラスとなることを積極的に行いたいと考えています」(坪内氏)

