連載 ユニオンルネサンス 第6 回 Part 1 全日本自動車産業労働組合総連合会(自動車総連) 会長 加藤裕治氏に聞く 労働組合は、企業と社会の パイプ役になる必要がある
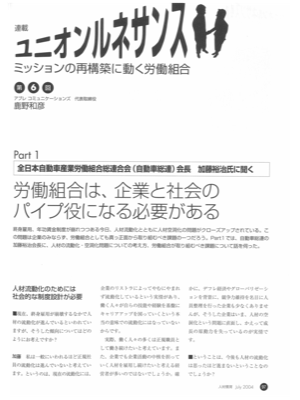
終身雇用、年功賃金制度が崩れつつある今日、人材流動化とともに人材空洞化の問題がクローズアップされている。この問題は企業のみならす、労働組合としても真っ正面から取り組むべき課題の一つだろう。 Parti では、自動車総連の加藤裕治会長に、人材の流動化・空洞化問題についての考え方、労働組合が取り組むべき課題について話を伺った。
人材流動化のためには社会的な制度設計が必要
現在、終身雇用が崩壊するなかで人材の流動化が進んでいるといわれていますが、そうした傾向についてはどのようにお考えですか?
加藤
私は一般にいわれるほど正規社員の流動化は進んでいないと考えています。というのは、現在の流動化には、企業のリストラによってやむにやまれず流動化しているという実情があり、働く人々が自らの技能や経験を基盤にキャリアアップを図っていくという本当の意味での流動化にはなっていないからです。
実際、働く人々の多くは正規職員として働き続けたいと考えています。また、企業でも企業活動の中核を担っていく人材を雇用し続けたいと考える経営者が多いのではないでしょうか。確かに、デフレ経済やグローバリゼーションを背景に競争力維持を名目に人員整理を行った企業も少なくありませんが、そうした企業はいま、人材の空洞化という問題に直面し、かえって成長の原動力を失っているのが実情です。
ということは、今後も人材の流動化は思ったほど進まないということなのでしょうか?
加藤
そうは思いません。働く人々の価値観が多様化し、ライフスタイルに合わせた働き方を求める人々が増加するなかで働き方そのものは多様化していくでしょうし、生活給から仕事の能力や役割に比重を置いた処遇制度へと変化していくなかで、転職することによってキャリアアップを図っていこうと考える人々が増えていくことは自然なことです。
しかし、そうした本当の意味での人材流動化を推進するためには、社会的な制度設計が必要です。少なくとも、同一業界内に共通した評価基準、能力や役割を社会的に評価できるような物差しが存在しなければ、安心してキャリアプランを描くことは困難だと思われます。

