Part 2 ケース 富士通エフ・アイ・ビー労働組合 組合員への情報提供と職場委員教育で、 雇用の多様化と働き方の個別化に対応

時代や環境の変化のなかで、労働組合としてのあり様を模索するところが増えている。とりわけ、変化の激しい情報サービス産業においては、組合員の個別化が進み、多様化した個人の価値観に応える活動が求められるといえるだろう。今回は、組合員サービスの多様化を目指しながら機関要員の育成に力を注いでいる富士通エフ・アイ・ピー労働組合の活動にスポットを当ててみた。
多様化する組合員の意識と拡大する執行部とのギャップ
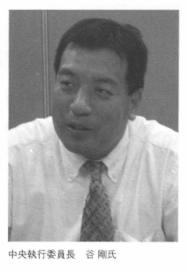
グローバリズムの進展や企業間競争の激化によって、働き方や処遇制度が大きく変化するようになった。とりわけ情報サービス産業においては、能力主義・成果主義の導入や仕事内容の個別化によって社員は大きなプレッシャーを感じている。多くの人たちがプレッシャーに打ち勝ち、やりがいや働きがいを感じながらいきいきと仕事に打ち込める環境を整えることが、労働組合の重要な活動として期待されている。
しかし、その一方で生き方や働き方についての価値観が多様化している状況もあり、これまで画一的な要求をメインに活動してきた労働組合と組合員の間に意識のギャップが広がっているのも現実だ。また、組合員のために良がれと思って取り組んだ活動も一部の人しかその恩恵を享受できず、そのことがかえって組合離れを加速するという現象も起きている。
富士通の関連会社でIT アウトソーシングやネットワークアウトソーシング、アプリケーションアウトソーシングを手がける富士通エフ・アイ・ピーも例外ではない。同労働組合の中央執行委員長、谷剛氏は、労働組合の抱える課題を次のように語る。
「これまでの労働組合は『労働条件の維持・向上による生活改善や雇用確保』を活動の基本にしてきました。このことは労働組合の本来的な活動である以上、今後とも基本的な活動として重視していくべきですが、問題は、画一的な活動では組合員の多様なニーズに応えることができないということ。その意味で、これからの労働組合は自らの活動を『サービス活動』として位置づける必要がありますし、どれだけ活動のウイングを広げられるかが大きな課題だといえます」
もっとも、活動内容が多様化すればするほど、その「サービス」を享受できる人間は隕られてしまう。個人個人のニーズに応じたサービスは、利用者からは高い評価を得られる半面、利用していない組合員からは不満の声が上がり、実際に組合員にとってどの程度有効であったかを検証できない弊害を招きやすいのである。
富士通エフ・アイ・ピー労組では、そうした状況を踏まえ、今年度の重点課題として広報活動と教育活動の2つの柱を重視することを打ち出すことになった。つまり冂青報伝達・収集」活動を充実させることで、多様化したサービス内容を全体化する取り組みを強化するとともに、それを可能にする人材の育成に取り組むことに一歩踏み出すことになったのである。

