連載 人事徒然草 第12 回(最終回) 社員としての自立に関する12 章
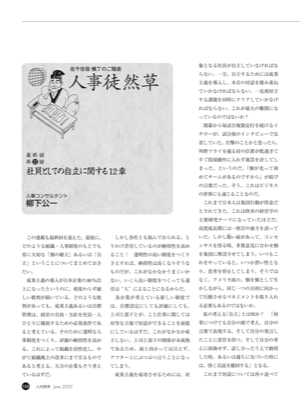
この連載も最終回を迎えた。最後に、どのような組織・人事制度のもとでも常に大切な「個の確立」あるいは「自立」ということについてまとめておきたい。
成果主義の導入が日本企業の80%以上になったというのに、相変わらず厳しい批判が続いている。どのような批判があっても、成果主義あるいは目標管理は、経営の目的・方針を社員一人ひとりに徹底するための必須条件であると考えている。そのために透明な人事制度をつくり、評価の納得性を高める。これによって組織を活性化し、やがて組織風土の改革にまで至るものであると考える。大方の企業もそう考えているはずだ。
しかし各社とも悩んでおられる。とりわけ苦労しているのが納得性を高めること!
透明性の高い制度をつくりさえすれば、納得性は高くなりそうなものだが、これがなかなかうまくいかない。いくら良い制度をつくっても運営は“人”によることになるからだ。各企業が考えている新しい制度では、目標設定にしても評価にしても、上司と部下とが、こと仕事に関しては対等な立場で対話ができることを前提にしているはずだ。これがなかなか成立しない。上司と部下の関係が未成熟であるため、面と向かっては言えず、アフター5にぶつぶつ言うことになってしまう。
成果主義を成功させるためには、対象となる社員が自立していなければならない。一方、自立するためには成果主義を導入し、本音の対話を積み重ねていかなければならない。一見相対立する課題を同時にクリアしていかなければならない。これが最大の難関になっているのではないか?
開幕から毎試合複数安打を続けるイチローが、試合後のインタビューで反省していた。打撃のことかと思ったら、外野フライを捕る肩の位置が低過ぎてすぐ投球動作に入れず進塁を許してしまった、というのだ。「個が光って初めてチームがあるのですから」が結びの言葉だった。そう、これはビジネスの世界にも通じることなのだ。
これまで日本人は集団行動が得意だとされてきた。これは欧米の経営学の主要研究テーマになっていたほどだ。高度成長期には一枚岩の強さを誇っていた。しかし脆(もろ)い面があって、コンセンサスを得る時、多数意見に合わせ個を集団に埋没させてしまう。いつもこれをやっていると、いつか習い性となり、思考を停止してしまう。そうではなく、アメリカ流の、個を個として生かしながら、同じ一つの目的に向かって行動させるマネジメントを取り入れる必要もあるのではないか。
私の考える「自立」とは何か?
「何事につけても自分の頭で考え、自分の言葉で表現する、そして自分の発言したことに責任を持つ。そして自分の考えに固執せず、話し合ったうえで納得した時、あるいは過ちに気づいた時には、快く自説を撤回する」となる。
これまで対話については再々述べてきたので今回は「自立するための条件」について考えてみた。

