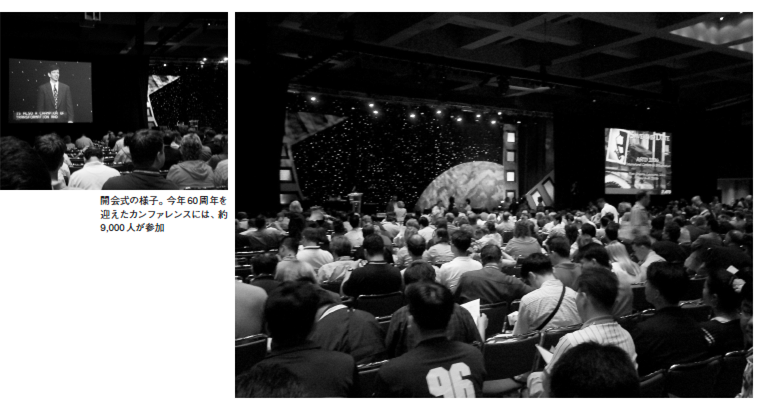海外情報 ASTD2005 職場で「学習が起きる場」をいかに つくるかがHRD の重要な役割に

ASTDインターナショナル・カンファレンス2005が、米国フロリダ州オーランドで6月5日~9日の期間、『YOUR TIME IS NOW.THE FUTURE IS CALLING(HERE)』というテーマで開催された。今年で60 周年を迎えたこのカンファレンスには、企業の人材開発関係者やコンサルタント、教育機関・行政体のリーダーなど約9,000人が参加した。参加国は72カ国で、韓国が327 人、日本からは214 人が参加していた。本稿では、このカンファレンスで発表された3人の基調講演と300以上のコンカレントセッション、およびEXPOの内容を踏まえ、人材開発の動向を筆者なりにいくつかのテーマに整理して論じてみたい。
HRDがファイナンスを理解する必要性
ASTDの今年のチェア(議長・委員長)はリタ・ベイリー氏で、プレジデント・CEOは、トニー・ビンガム氏が昨年に引き続き担当している。開会の挨拶でビンガム氏は、ワークスペース・ラーニング(職場での学習)によるプロフェッショナル・パフォーマンスの向上の重要性が高まっていることをあげていた。米国では470 万人が失業している反面、実際には67%の組織が新しいスキルの必要性に直面している。しかし、組織内部では必要なスキルをカバーできないため、その47%が外部から調達しているそうだ。そこで組織は、どんなスキルが将来必要なのかを組織メンバーに理解させ、ダウンサイジングが起きないように、スキルの足りない人に変化にコミットするように推進していく必要があると語っていた。それとともに、ラーニング・トレーニング担当は、スキルギャップを埋めるためのコンピテンシー開発の計画を策定して、組織能力を高めるようにしていかなければならない。それを実現するには、ラーニング・トレーニング担当CLOやHRが組織全体に認知されるように、リーダー(経営層)とのパイプラインをつくり、ビジネスパートナーになっていく必要がある。そのためには、リーダーと話し合いができるようにファイナンスを理解しなければならないと訴えていた。
他のセッションでも、「ファイナンスのことを理解しよう」という発言が多く見受けられた。これは、人材開発スタッフの影響力を高めるためには、経営層や予算を管理している部門に対して、彼らが受け止められる言葉で語ろうということである。この内容は、パフォーマンスコンサルタントで有名なデーナ・ロビンソン氏の「どうしたら経営会議の席を獲得できるか」といったセッションでも紹介されていた。
また、「レベル4」の研修効果測定で有名なドナルド・カークパトリック氏の息子であるジェームス・カークパトリック氏は、レベル4とBSC(バランス・スコア・カード)を合体する方法を紹介していたが、その試みも同様の狙いがあろうかと思う。
これは、筆者の推測であるが、この背景には伝統的なクラスルーム・トレーニング(座学による集合研修)に企業側が予算を出さなくなっている傾向があり、それに対する人材開発部門の抵抗かと思われる。しかしながら、よりパフォーマンスに密着しているワークスペースの研修やAI などのミーティングには、先進的な企業が予算を惜しんでいるようには見受けられない。もしかすると、古い学習モデルや学習プロセスにこだわり、組織のなかでいま起きている変化に対応できない人材開発スタッフが、経営側からROI(投資効率)などで淘汰されてきたのではないだろうか。
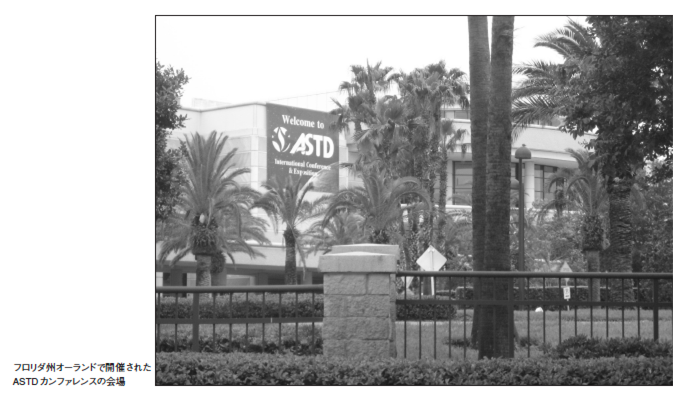
ROI の変化
研修のROIをテーマにしたセッションの数は、昨年に比べて減少している印象があった。セッションの内容も、従来のROIを取らなければだめだという強い調子が消えて、すべての研修にROI が必要ではなく、計測できない大事なものもあるのだという論調に変化してきている。研修効果測定の「5 段階モデル」で有名なジャック・フィリップス氏のセッションでも、ROI を実際に測定しているのは、企業の5 %程度であるといった紹介をしていた。また、リン・シュミット氏とジョン・ミラー氏のセッションでは、ROI の算出方法として、生み出した業績額に対してプログラムの貢献度(%)をかけ、さらに信頼度(%)をかけることでアウトプットを算出し、それを費用で割るという方法を紹介していた。
また、これと同様の方法でROIを算出した事例が、ASTD の賞を受賞していた。これは、ブース・アレン・ハミルトンのバニーダ・パーカー・ウィルキンス氏のセッションで、エグゼクティブ・コーチングの導入に当たって、コーチングのROI を測ったものである。その手順は、どういうアウトプットが欲しいのかを経営層にまず聞き、その結果、顧客との関係やチームワークなどの8項目を選択したそうである。そして、8項目それぞれについてどのような伸びがあったのか、受講者に伸びた金額を聞き、その額の高い上位二人をデータから省いたものに、貢献度と信頼度をかけて、さらにそれを50%にするという計算方法だった。事例では、その結果ROI が600 %であったということである。論理的な根拠の希薄な、荒っぽいやり方ではあるが、この事例に対してASTD側が賞を授与したということが、ROI の今後の動向を占う意味で興味深いと思う。こういった背景には、ROIは理屈ではきれいだが、実際に企業内部でやってみると、手間はかかるし、根拠が希薄で説得力に欠けるという結果が出たのではないだろうか。
また、別のセッションでは、ROI といった現在の価値を測るものではなく、EVA(企業経済価値)といった将来にわたる価値を測定していく方法を模索したらどうかという提案も出ていた。
研修の効果測定をさまざまな方法で行うことは大切だが、ROI までを無理して取る必要はないという傾向に落ち着きそうである。