新連載 ユニオンルネサンス 第1回 Part 1 日本労働組合総連合会(連合) 会長笹森清氏に聞く 労働組合は転換期を迎えた。 だから、あるべき姿を明確にする

日本の産業構造が大きな転換期を迎えているいま、働き方や暮らし方も大きく変わろうとしている。当然、働く人々で構成される労働組合もそのあり方が問われており、労働組合としての存在意義、運動の方向性についての再構築が急務になっているといえるだろう。本連載では、「ユニオンルネサンス」と題して、ミッションの再構築を図る労働組合の現状と課題、未来展望についてレポートする。第1回目の本号では、労働組合最大のナショナルセンター・連合会長の笹森清氏にご登場いただき、労働組合の課題および労働運動の目指すべき方向性について話を伺った。
働く者が結集する組織になり切れていない労働組合
いま、労働組合の存在意義、ミッションの再構築が求められています。これまでの労働運動を振り返った時、労働組合のあり様はどのように変わってきたとお考えでしょうか。
笹森
過去の労働運動の歴史をたどってみると、[ 抵抗型]「要求型」「参画型」へと変化し、いま、新たに「共生型」とでもいうべき労働組合運動への脱皮が図られているように思います。わかりやすくいえば、以前の労働組合は目的が1つ。多くの組合員が結集できる抵抗すべき課題や要求があり、その御旗の下に多くのエネルギーを結集できたわけです。しかし、時代が変化するなかで、組合員の価値観や意識が多様化し、労働組合は大きな転換期を迎えているといえます。
連合では、新たな労働運動構築に向けてさまざまな取り組みをなされています。また、最近では、外部の識者による「連合評価委員会」を組織し、これからの労働組合についての提言を受けられましたね。
笹森
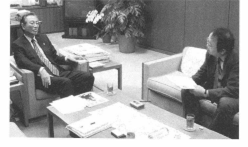
連合は、それまで4分割されていたナショナルセンター(総評、同盟、中立労連、新産別) を統一して結成されたわけですが、統一という目標を達成した段階で、その後の展望やナショナルセンターの役割が逆に見えなくなった感があります。よく90 年代は「失われた10 年」と称されますが、労働運動にとっても90 年代は「失われた10年」。新たな労働運動を模索する時代が続き、連合としてもこれまでの運動を振り返るとともに、21 世紀の労働組合にふさわしいビジョンを策定するために努力を重ねてきたところです。
評価委員会の設置もそうしたビジョン策定の一環であり、とかく内部完結型になりがちな労働組合の内向きの議論を排し、外部の識者に率直に指摘していただくことで、あるべき方向性をより明確にしたいと考えたのです。

