第35回アメリカ留学がビリギャルの呪縛を解いた 挑戦する私のマインドセット小林 さやか氏 教育研究者/ビリギャル本人
 小林 さやか氏
小林 さやか氏
映画『ビリギャル』のモデルとして、一躍時の人となった小林さやかさん。
各地で講演活動を続けるうち、日本の教育の在り方を考えるようになり、ウェディングプランナーから一転、大学院への進学を果たした。
現在はアメリカで学ぶ、さやかさん“らしさ”を築いたものとは。
[取材・文]=たなべやすこ [写真]=小林さやか氏提供
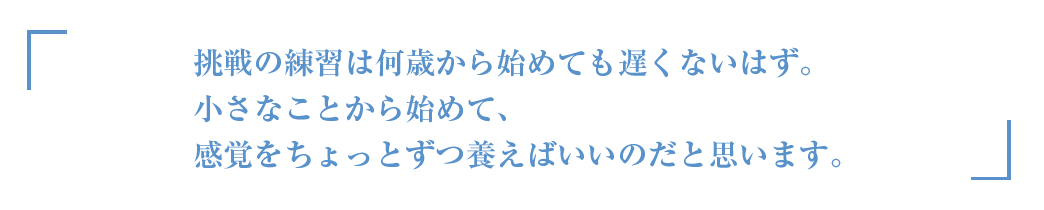
挑戦の練習をさせてくれた破天荒な母の存在
―― さやかさんがアメリカ留学を始めて、2年近くたちます。日本との違いをどこに感じますか。
小林さやか氏(以下、敬称略)
『ビリギャル』のヒットをきっかけに日本各地の学校などを回るうち、子どもを取り巻く学習環境に関心が向くようになりました。日本の大学院を修了後、アメリカのコロンビア大学教育大学院に進学し、認知科学を専攻しています。2年間の留学はハードでしたが、あっという間でしたね。
日本と海外の学生を比べるなら、その違いは学生の姿勢でしょうか。一概にはいえませんが、私が見る限り、学び手のパッションが違う。コロンビア大学には、世界各国から学生が集まります。中国や韓国のように日本以上に学歴がものをいう国もあれば、北欧のように純粋な興味や関心を大切にする国もある。また、アメリカのように成績が卒業後の就職活動等に直接影響する場合、学生が教授に「なぜこの評価なんだ!」と食ってかかることも珍しくありません。いずれにせよ、自分の意志に基づいて行動する人が圧倒的多数のように感じました。
―― さやかさんも情熱に溢れ、ご自身の意志のもとに行動しているように映ります。
小林
確かに行動力はある方だと思います。感情がわっと揺れると、いてもたってもいられなくなっちゃう(笑)。高校生のころ、坪田先生※に初めて出会ったときも、「やっべ、すごい大人に会っちゃった。もう絶対ついていく!」って思ったんですよ。そこから受験勉強を始めて、大変なこともたくさんあったけど、頑張っているというより、勝手に走りだしちゃった感覚。感情の起伏が激しい方なので(笑)、それがいい方向に爆発するとものすごいエネルギーを発して走れる。特に、ワクワクさせてくれる人に出会ったときにそうなる傾向がありますね。
でも近ごろ思うのは、私を見て、つらくなっちゃう人って結構いるんじゃないかなって。だって私、常に前向きでバイタリティに溢れているように見えるでしょう? 「さやかちゃんみたいに頑張れない」と言う人がいるけど、実際私だって自信を失くしたり落ち込むことだってあるし、頑張りたくない日の方が多いですよ。私は、少しずつ「挑戦の練習」をしてきただけなんです。やっぱり小さなことから始めるべきですよ。挑戦って、「練習」が必要なんだと思います。
※坪田信貴氏。さやかさんが高校時代に通った個別指導塾の講師で、『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』(KADOKAWA)の著者。
―― 挑戦の練習?
小林
そう。いきなり大きなチャレンジなんて、怖くてできるかーい! って。挑戦という体験を、少しずつ自分の体や心に教えていくのが大事で。私の場合でいえば、母がまあ、ぶっ飛んでいて。普通の親御さんなら「危ない!」って先回りして取り上げてしまうことを、あえて体験させるんですよね。仮に転んで血だらけになっても「そこが危ないって、わかってよかったね」って(笑)。母は私たちが体験から学ぶ力があると、信じてくれていました。改めて振り返ると、挑戦の練習を無意識のうちにさせてもらえていたのだと思います。
―― お母さまの影響が大きいのですね。
小林
そりゃもう! 母がビリギャルストーリーの主人公といっても過言ではありません。認知科学でも、親がどんなマインドセットを持っていて、どんな言葉かけをするかは子どものパフォーマンスに大きな影響を与えることがわかっています。
ビリギャルは、バカだった子が猛勉強して慶應に合格したみたいに映るけれども、実際はそんなにシンプルな話ではなく。当時の私の学習環境がどうであったかをよく見てほしいですし、「頑張れないのは、あなたの性格や資質のせいではないんだよ」と、多くの人に伝えたいです。
そして挑戦の練習は何歳から始めても遅くないはず。小さなことから始めて、感覚をちょっとずつ養えばいいのだと思います。
教育は憧れ ロールモデルが学ぶ文化を培う
―― 企業は社員に向け、学びの意図や目的に基づき研修などの機会を提供しますが、残念ながら自分の学びとして受け取れない人もいます。
小林
周りが期待する行動をとらないのは、動機づけが足りないのだと思います。モチベーションの授業で学んだExpectancy Value Theory(期待値価値理論)では、Expectance(期待値)とValue(価値)の2軸が本人のモチベーションに起因すると考えます。
課題は自分自身が「これなら頑張れば達成できる」と思えるかどうかのレベル感が重要で、タスクが簡単すぎても難しすぎても、モチベーションは上がりません。同時に「これをやることは自分にとって価値がある」と、どれくらい強く思えるかも大切です。極端な話、「慶應に行けばイケメンに会える!」でも、本人にとってそれだけ価値が感じられるものなら十分な動機づけになり得ます。
その点で言うと、日本の学校教育はExpectanceとValueの、どちらもうまく満たせていないように見えますよね。個々人の習熟度を無視した一斉授業は、本人の能力に見合っていないレベルの勉強を強いられている子どもが必ず出てくるし、「なんのために学ぶのか」という問いを置いてきぼりにしてしまっている。テスト結果を重視した、学びと暮らしを切り離した指導によって、価値を感じられないものがとても多い。
私たち大人が学校でExpectanceとValueが満たされる体験をあまりしてこなかったから、子どもたちにもうまく教えられないという、構造的な問題があるように感じます。
―― 大人の学びでは、主体性が強く求められます。意欲を引き出すには、マインドセットが大事になるのでは。
小林
そのとおりです。特に学びを届ける人、学びを導く人―― 上司など、指導する立場の方がロールモデルになるのが大事だと思います。学びに励み成長する姿を見せることで、「素敵だな」と後進に思われる存在に なれば、仕組みを押しつけるよりも効果的ではないでしょうか。坪田先生はよく「教育は憧れ」と言いますが、私もそう思います。学びのモデルの存在が、組織に学ぶ環境を築き、学ぶ文化を培っていくのです。
―― さやかさんの書籍には、お母さまや坪田先生の他にも、お手本となる方が何人も登場します。
小林
私は人が好きで、「あの人みたいになりたい!」と思える人を見つけたら、とにかくまねをする、その人の道を後追いするのがスタイル。本人にアプローチして、「○○さんが今の私だったら、どうします?」って聞いちゃうんです。
――自身の「知りたい」に従う素直さが、学びを深めるのでしょうね。
小林
素直すぎるようで、坪田先生には呆れられています(笑)。この率直さが誰かを傷つけたり、私自身が傷を負うこともありますし。
ただ、ひとつ言えることは、つまずきを失敗だと思っていないところ。つまずきから得る学びを体感的にわかっているから、貪欲に克服しようとするんでしょうね。落ち込んで動けなくなるということはほとんどないかも。むしろそこにとどまっていると、心がズキズキする(笑)。「この経験をどうプラスにしよう」と、アクションに移して気を紛らわす方が、私には合っている気がします。
―― 失敗は悪いことではないと。
小林
悪いわけがない! 何だろう、日本の社会って、失敗を必要以上に怖がらせるところがありますよね。これ、本当によくないと思う。“初めて”に失敗はつきもので、そこから学んでブラッシュアップしていくことで完成に近づいていくものなのに。「失敗をするな」というのは、「挑戦をするな」、「成功をするな」と言っているようなものですよ。
さらに成功している人を見て、「才能があるから」で片づけるのも本当によくない。それだけなわけねーだろ! って。金メダリストだって、自身の課題に何度も挑んで、失敗もしながら実力を積み上げてきたはずです。
失敗に対するイメージは、事象を評価した結果にすぎません。事象の捉え方は、周囲の影響を大きく受けます。たとえば私の母は、子どもたちが失敗をポジティブに捉えられるようにと意識しながら、私たちと接してくれたのだと思います。
―― 失敗に不寛容な組織では社員の行動は消極的になり、本当の意味での組織貢献を妨げてしまうといったことが起こりがちです。
小林
ちょうど取材の直前に、Organizational Psychology(組織心理学)の授業で「組織カルチャーを築くもの」について議論したところで、主に2つの要素で盛り上がりました。
1つは、ファウンダーやリーダーの信念から形づくられるもの。思いを共有し、認知されていくことで築かれる文化です。たとえばトップが失敗を許さないという信念の持ち主なら、それが組織の文化になっていく。逆に挑戦が正しいと信じて止まない社長のもとでは、挑戦を歓迎する組織文化が築かれるという話でした。
そしてもう1つは、重要な出来事が起こったときの経営者や上司の態度や反応なんだそうです。たとえば会議で部下が上司に対して指摘をしたとき、「よく気づいてくれた!」と称賛したら、建設的批判も恐れない組織になるでしょう。でも「お前はクビだ」と返されたら、もう誰も上司には逆らえなくなってしまいます。
ここで大事なのは、部下たちは上司や経営者の態度を細かく観察している点です。イベントで何を発したか、共に働く仲間の言葉にどうリアクションしたかというのは、働き手のマインドセットや行動に、ものすごく強い影響を与えるはずです。
ビリギャルの呪縛を解き社会を変える挑戦へ
―― さやかさんは『ビリギャル』によって、人生が一転しました。注目される存在に変わっていくなかで、戸惑いはなかったのでしょうか。

小林
今思うと、“周りの思うビリギャル像”を勝手に背負い込んでいたところがありましたね。渡米直前の頃は、「私、挑戦しなくちゃ。だってビリギャルだから。みんなのロールモデルじゃなくちゃ」って、自分のお尻を引っぱたいて、無理やり頑張ってたところがあった気がします。
私自身は天才でも何でもなく、本当に普通の人。本当に多くの人となんにも変わらなくて、今でも勉強しながら5分に1度はスマホを覗いてしまって、罪悪感に苛まれる有様で。なのに、私を「努力の天才」と言ってくれる人がたくさんいる。そのギャップに苦しむこともありました。私そんなにすごくないんだけどなって。
でもアメリカでは私のことなんて誰も知らない。「ビリギャルだったんです」って言っても通じないですから(笑)。そもそも、みんな、他人のことなんてあんまり興味ないので、伝わったとて「だからなに?」で終わると思いますね。そうした環境で過ごすうちに、ようやく最近、自分が勝手につくっていたビリギャルの呪縛から解かれた気がします。
―― ビリギャルのイメージが留学を後押しし、留学先でマインドセットが変わっていったのが興味深いです。
小林
もちろん渡米はやりたいことがあっての選択です。けれども「ビリギャル」と呼ばれることなく、ウェディングプランナーをやり続けていたら、留学なんておそらく一生しなかった。ビリギャルで世界が広がったのは確かで、本当に感謝しています。だけど日本でビリギャルとして講演活動をしていた7年間のうちに、ニーズに応えるあまりに「自分らしく生きる」をちょっと置いてきぼりにしちゃってたかもな、と。そのことに気づく留学期間でもありましたね。
―― これまでの学びを、今後どのように生かしていきたいですか?
小林
私はやっぱり環境に恵まれていたと思っていて。母や坪田先生のような大人が側にいたから成功体験を積むことができて、こんなに遠く、当時は想像もつかなかった世界にまで来れた。学習環境の影響力のデカさを痛感してきた人生だった。
だから、私は「大人の教育」に興味があります。大人のマインドセットを変え、子どもへの言葉かけ、ほめ方、行動の促し方を変え、挑戦の練習ができる社会へと変えていきたい。
失敗を認め、挑戦する人をもっとまっすぐに応援できるようになったら、もっといきいきと、活気に溢れた世界になると思うんです。



