ケース4 三菱重工業 「ASPIRE to be」 技術者としての大志、夢実現の 入り囗となる配属予約採用
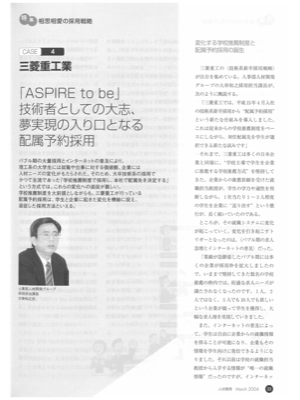
バブル期の大量採用とインターネットの普及により、理工系の大学生には就職や仕事に対する価値観、企業には人材ニーズの変化がもたらされた。そのため、大卒技術系の採用でかつて主流であった「学校推薦制度で採用し、本社で配属先を決定する」という方式では、これらの変化への追従が難しい。学校推薦制度を大前提としながらも、三菱重工が行っている配属予約採用は、学生と企業に起きた変化を機敏に捉え、追従した採用方法といえる。
変化する学校推薦制度と配属予約採用の誕生
三菱重工の〈技術系新卒採用戦略〉が注目を集めている。人事部人材開発グループの大串和之採用担当課長が、次のように概説する。
「三菱重工では、平成15 年4月入社の技術系新卒採用から“配属予約採用”という新たな仕組みを導入しました。これは従来からの学校推薦制度をベースにしながら、初任配属先を学生が選択できる新たな試みです」
それまで、三菱重工は多くの日本企業と同様に、“学校主導で学生を企業に推薦する学校推薦方式” を堅持してきた。企業からの推薦依頼を受けた就職担当教授か、学生の学力や適性を判断しながら、1社当たり1~ 3人程度の学生を企業に“送り出す”という慣行が、長く続いていたのである。
ところが、その就職システムに変化が起こっていく。変化を引き起こすトリガーとなったのは、くバブル期の求人急増とインターネットの普及〉たった。
「業績が急膨張しかバブル期には多くの企業が採用枠を拡大しましたので、いままで堅持してきた数名の学校推薦の枠内では、旺盛な求人ニーズが満たされなくなったのです。
1人、2人ではなく、5人でも10 人でも欲しいという企業が競って学生を獲得し、大幅な求人増を実現していきました。
また、インターネットの普及によって、学生は自由に企業からの就職情報を得ることが可能になり、企業もその情報を学生向けに発信できるようになりました。それ以前は学校の就職担当教授から入手する情報が“唯一の就職情報” だったのですが、インターネッ卜の普及によって、企業と学生が双方向で情報をやり取りすることが可能になりました。こうした状況の変化によって、学生は自らの意志で自ら希望する企業の門を叩くことが可能になったのです」(大串氏)
就職に関する大きな環境の変化によって、企業と学生の“距離”は確実に短縮されていった。
では、“就職革命”の変化は、いったい何をもたらしたのだろうか。次の2点に注目したい。

