連載 新しきは足下にあり 第11 回 利休に学ぶ「勤労観」
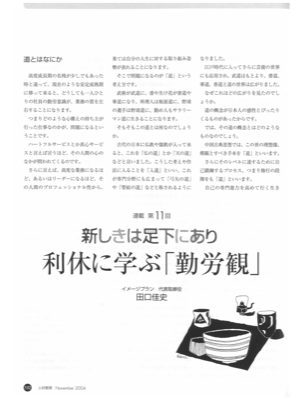
道とはなにか
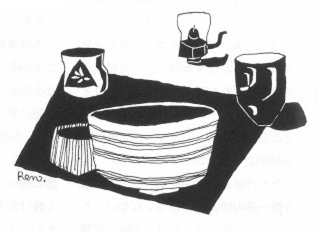
高度成長期の名残が少しでもあった時と違って、現在のような安定成熟期に移って来ると、どうしても一人ひとりの社員の勤労意識が、業務の質を左右することになります。
つまりどのような心構えの持ち主が行った仕事なのかが、問題になるということです。
ハートフルサービスとか、真心サービスと言えば言うほど、その人間の心のなかが問われてくるのです。
さらに言えば、高度な業務になるほど、あるいはリーダーになるほど、その人間のプロフェッショナル性から、果ては自分の人生に対する取り込み姿勢が表れることになります。
そこで問題になるのが「道」という考え方です。
武術が武道に、書や生け花が書道や華道になり、料理人は板前道に、野球の選手は野球道に、勤め人もサラリーマン道に生きることになります。
そもそもこの道とは何なのでしょうか。
古代の日本に仏教や儒教が入って来ると、これを「仏の道」とか「天の道」などと言いました。こうした考えや作法に入ることを「入道」といい、これが専門分野にも広まって「弓矢の道」や「管弦の道」などと称されるようになりました。
江戸時代に入ってさらに芸能の世界にも応用され、武道はもとより、書道、華道、香道と道の世界は広がりました。
なぜこれはどの広がりを見たのでしょうか。

