連載 「偶然」からキャリアをつくる 第11 回(最終回) ~“意図的”にキャリアをつくってこなかった人たち~ EQ からPlanned Happenstance な10 人を検証する
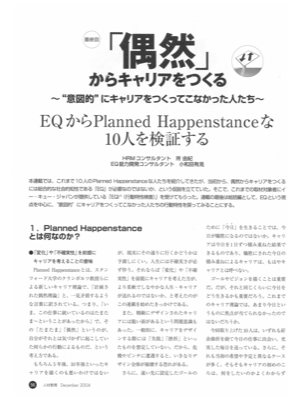
本連載では、これまで10人のPlanned Happenstance な大たちを紹介してきたが、当初から、偶然からキャリアをつくるには総合的な社会的知性である「EQ 」が必要なのではないか、という仮説を立てていた。そこで、これまでの取材対象者にイー・キュー・ジャパンが提供している「EQ ド(行動特性検査)」を受けてもらった。連載の最後は総括編として、EQ という視点を中心に“意図的” にキャリアをつくってこなかった大たちの行動特注を探ってみることにする。
1 . Planned Happenstanceとは何なのか?
「変化」や「不確実性」を前提にキャリアを考えることの意味
Planned Happenstanceとは、スタンフォード大学のクランボルツ教授らによる新しいキャリア理論で、「計画された偶然理論」と、一見矛盾するような言葉に訳されている。つまり、「いま、この仕事に就いているのはたまだま~ということがあったから」で、その「たまたま」「偶然」というのが、自分がそれとは気づかずに起こしていた何らかの行動によるものだ、という考え方である。
もちろん5年後、10年後といったキャリアを描くのも悪いわけではないが、現実にその通りに行くかどうかは予測しにくい。人生には不確実さが必ず伴う。それならば「変化」や「不確実性」を前提にキャリアを考えた方が、より柔軟でしなやかな人生・キャリアが送れるのではないか、と考えたのがこの連載を始めたきっかけである。
また、精緻にデザインされたキャリアには脆い面があるという問題意識もあった。一般的に、キャリアをデザインする際には「失敗」「挫折」といったものを想定していない。だから、危機やピンチに遭遇すると、いきなりデザイン全体が崩壊する恐れがある。
さらに、遠い先に設定したゴールのために「今日(いま)」を生きることでは、今日が犠牲になるのではないか。キャリアは今日を1日ずつ積み重ねた結果できるものであり、犠牲にされた今日の積み重ねによるキャリアは、もはやキャリアとは呼べない。
ゴールやビジョンを描くことは重要だ。だが、それと同じくらいに今日をどう生きるかも重要だろう。これまでのキャリア理論では、あまり今日というものに焦点が当てられなかったのではないだろうか。
今回取り上げた10 人は、いずれも紆余曲折を経て今日の仕事に出会い、充実した毎日を送っている。さらにそれも当初の希望や予定と異なるケースが多く、そもそもキャリアの初めのころは、何をしたいのかよくわからず悶々としていたという人がほとんどだった。
そんななかで、全員に共通しているのは、その時々の自分をよく見つめ、どうしたいのか自問し、感性や直感を使って行動していることである。これは以下にあげた、クランボルツ教授によるPlanned Happenstance理論における「5つのスキル」とも重なる。
①好奇心(Curiosity)
②粘り強さ(Persistence)
③柔軟性(Flexibility)
④楽観性(Optimism)
⑤リスクテイク(Risk Taking)
だからこそ、これまでどちらかといえば日本社会でよろしくないとされていた行動様式~いまを楽しむ、直感を信じる、あえて行動する~といったことに、もう一度着目したいと考えた。より自然で人間的なキャリアを送るには、Planned Happenstance はとても有効な理論ではないだろうか。そして、デザイン通りのキャリアよりもPlanned Happenstance なキャリアの方が、実は多くの人から納得感や共感を得られるのではと、密かに確信している。
2. 「EQI®」検査結果から見た傾向
EQ の高い大とは、「感情」に賢い人のことである
EQ (Emotional InteⅢgence Quotient)とは、自分の「感情」を的確に把握し、その場に応じた適切な行動を取るために自分の「情動(感情の動き)」をマネジメントする能力である。それは、自分や他者の「気持ち」がわかる能力であり、自己理解と相互理解の基礎となっていくものだ。言い換えれば、EQ の高い大とは感情に賢い人のことであり、EQ は社会生活を送るうえで欠かせない“社会的知能”の一つといえるだろう。
現在、ビジネスは複雑化し業務も細分化してきており、個々人がお互いの専門性を持ち寄っで“協業”していくタイプの仕事が増えている。そこでは、これまで以上にチームや組織としての成果が問われてくる。このような状況下で優れたパフォーマンスを発揮するにはIQ も重要だが、感情やこころの問題、コミュニケーションのありようを扱うEQ が優れていることも、大切な要件となってきている。
ところで、EQI®の高さは決して単一の要素で決まるものではない。EQは、自分で自分の状態がわかる「心内知性(セルフ・コンセプト)」、他者に適切かつ効率的に働きかけることができる「対人関係知性(ソーシャル・スキル)」、そして自分と他者の両者の状態を同時に認知できる「状況判断知性(モニタリング能力)」の3つの「知性」で構成されている。この3つの知性をどの程度備えているか、および3つの知性のバランスがどの程度良いかということでEQ の発揮度合いは決まる。さらにこの3つの知性は、8つの「能力」、そして24 の「素養」に分けられる(図表1 )。
取材した10 人は、恐らくこのEQI®の結果がバランス良く高い水準を示し、それがキャリアのあり方にも影響を与えているのではと考えた次第だ。なお今回、調査として用いた「EQI®」とは、EQ という知能を通して、最終的にアウトプットしている「現在の行動傾向( クセ)」を測るものである。そして驚いたのは、10 人の傾向が非常に似通っており、前述したPlannedHappenstance 理論における「5つのスキル」を示していたことだ(図表2は10 人の平均値を掲載している)。
ちなみに参考として、10 人と同じくらいの年齢層(40 歳代)で、彼らとは非常に対照的なキャリア、かつ管理職(メーカー勤務) の人たちのEQI®結果を、合わせて紹介しておいた。もちろん、全員がこのような波形ではないが、その結果は、レーダーチャート図を見てもわかるように、Planned Happenstanceな人だちと比べ、非常に対照的なものとなっている。


