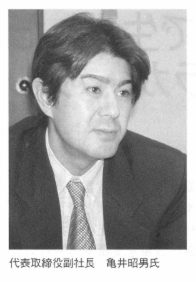WAVE 仙台コカ・コーラボトリング 中期経営計画を達成する目的で生まれた 5ヵ年計画の「仙台コカ・コーラカレッジ」

フリーライター
浅久野 映子
我々は生まれ変わる。そして、会社も
仙台コカ・コーラボトリングが、5ヵ年計画の「仙台コカ・コーラカレッジ」を開講したのは、2002 年8月である。それまでにも同社は、新入社員研修を始め中堅社員研修、管理職研修といった階層別の教育制度を持ち、とりたてて研修に不熱心というわけではなかった。しかし従来の教育とは異なり、カレッジは全社員を対象とし、①より高い専門性の習得や新しい考え方、行動力を身につけるための能力開発を行う、②自己啓発を通じて自己変革を成し遂げる者に会社が教育機会の提供やその環境づくりをサポートする、③講義日程に合わせて受講生各自が日程調整して自主参加することで自主自立の精神を養う、という3つの狙いを持っている。
そもそもカレッジは、同社の2002年からの3ヵ年の中期経営計画を達成するために創設されたものである。“Re-Born21 ”と名づけられた中期経営計画は、“Re-Born21 我々は生まれ変わる。そして、会社も” を合言葉に、売り上げと利益を確保できる体質を構築すべく抜本的な構造改革に取り組んだものだった。
同社が生まれ変わらなければならないと自覚するほどの危機感を持つに至るには6つの要因があった。
第1は「販売チャネルの大きな変化」。酒屋や食料品店などの個人商店が減少し、大型の量販店やスーパーマーケットが増大。量販店やスーパーマーケットは、販売ボリュームは大きいものの個人商店に比べると利益率が低い。販売数量が伸びたとしても利益が伴わず、経営は苦戦を強いられることになる。実際、売り上げはここ数年横ばいといった状態だったが、利益率は下かっていた。
第2は「デフレによる価格の下落」、第3は「飽和状態にある屋外自動販売機の設置」。飲料事業にとって自販機ビジネスは、値引きしなくていい、収益性の高い販売チャネルである。ただし、屋外の自販機は1台当たりの売り上げは必ずしも高くない。自販機が国道沿いに設置されている場合にはこれは顕著で、しかもこういった場所にある自販機はメンテナンスにも手開かかかる。そのため今後は、屋内の自販機の設置により注力する必要があった。屋内に自販機を設置する場合、ほとんどが法人相手となり、よりハイレベルな営業活動が求められる。
第4は「競合他社の台頭」で、第5は「意識改革の欠如」だ。「社内の風土にもかかわることだが」と代表取締役副社長・亀井昭男氏は前置きしたうえで、これはコカ・コーラのブランドカが強かったがゆえの悲劇だと説明した。
「とかく、われわれは過去の成功体験にしがみついてしまいがちです。これまでのわが社の営業は、体育会系とでもいうのか、労力を惜しまない姿勢でお客さまの心をつかむスタイルを武器にしていたのです」
そのため、同社の営業マンはブランドカに頼らないビジネス的な会話と提案力が弱いと亀井氏は指摘する。加えて、販売数量さえ伸ばせば収益も上がるという右肩上がりの時代の成功体験から、販売数量重視の営業を良しとする雰囲気が社内にはあり、それは同時に損益意識の希薄さを伴った。
そして第6は「以上の5点に対する経営陣の強い危機感」である。だからこそ同社は、違う会社に生まれ変わろうとしたのである。
成果を上げるうえで必要な教育を提供