CASE1 セイコーインスツル 3 つの地区や仕事の特性を考慮した、 中国現地法人における 「評価・報酬制度」の再構築
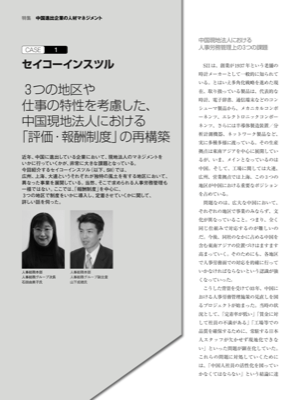
近年、中国に進出している企業において、現地法人のマネジメントをいかに行っていくかが、非常に大きな課題となっている。今回紹介するセイコーインスツル(以下、SII)では、広州、上海、大連というそれぞれが独特の風土を有する地区において、異なった事業を展開している。当然、そこで求められる人事労務管理も一様ではない。ここでは、「報酬制度」を中心に、3つの地区で制度をいかに導入し、定着させていくかに関して、詳しい話を伺った。
中国現地法人における人事労務管理上の3つの課題
SII は、創業が1937 年という老舗の時計メーカーとして一般的に知られている。とはいえ多角化戦略を進めた現在、取り扱っている製品は、代表的な時計、電子辞書、通信端末などのコンシューマ製品から、メカニカルコンポーネンツ、エレクトロニックコンポーネンツ、さらには半導体製造装置/分析計測機器、ネットワーク製品など、実に多種多様に渡っている。その生産拠点は東南アジアを中心に展開しているが、いま、メインとなっているのは中国。そして、工場に関しては大連、広州、営業拠点では上海、この3つの地区が中国における重要なポジションを占めている。
問題なのは、広大な中国において、それぞれの地区で事業のみならず、文化が異なっていること。つまり、全く同じ仕組みで対応するのが難しいのだ。今後、同社のなかに占める中国を含む東南アジアの位置づけはますます高まっていく。そのためにも、各地区で人事労務面での対応を的確に行っていかなければならないという認識が強くなっていった。
こうした背景を受けて03年、中国における人事労務管理施策の見直しを図るプロジェクトが始まった。当時の状況として、「定着率が低い」「賃金に対して社員の不満がある」「工場等での品質を確保するために、常駐する日本人スタッフが欠かせず現地化できない」といった問題が顕在化していた。これらの問題に対処していくためには、「中国人社員の活性化を図っていかなくてはならない」という結論に達したのは容易に想像がつくだろう。「そのためには、まず人事労務管理上の課題を明らかにしなければなりません。課題を抽出するために、拠点ごとの問題点の洗い出しを行いました。われわれとしては、活性化に対するヒアリングを実施したつもりだったのですが、問題点はそれだけに止まりませんでした」と驚きの表情を見せるのは、人事総務本部人事総務グループ副主査・山下成徳氏。
具体的に言うと、「賃金がどうやって決まっているかわからない」はまだしも、「食事をおいしくしてほしい」「シャワーの出をよくしてほしい」「誰が総経理(会社責任者)なのかわからない」など、非常に多岐に渡っていた。そして、分析を重ねた結果、大きく3つに課題をまとめることができた。
1. 人事労務管理の重要性に対する現地責任者の認識不足
製造ラインを立ち上げることが中心となってしまい、日本人の現地責任者は人事労務管理面まで手が回っていなかった。事実、中国内における人事労務に関する知識や実態を把握しないまま経営に当たっていたという。
2. 人事制度への信頼感・納得感の欠如
人事制度が日本の古い制度をベースに設計されており、賃金などが年功的になっていた。そのため、中国人社員から見て賃金・評価に対する納得性が薄かった。
3. 人事スタッフの知識・スキル不足
現地では、日本人スタッフの指示に従うことが評価されると信じているローカルスタッフが多く、事業・環境等により制度を抜本的に変えたり、問題を解決するための、提案をすることは、特に求められていなかった。当然、中国のローカル人事スタッフにも必要な知識・スキルが身についていなかった。
「以上の3点に重点を置き、各拠点での実情に合わせて人事労務の各種制度改革に着手することになったというわけです」(山下氏)。
拠点によって異なる人事労務管理上の問題点
では、地区ごとの人事労務管理上の問題点を明らかにしてみよう。
●広州地区
1つ目は「年功型の評価」。2つ目は「人材の入れ替わりが激しい」。それこそ3カ月もてばいいという状況だった。毎日のように入社する人がいて、人事担当者は採用業務に忙殺されていた。そして、3つ目が「無期限雇用契約」という中国特有の法律である。
中国では同一企業で雇用が10年を超えると、本人が希望すれば当該地区の定年まで勤めることができる権利が生じる。だから現地企業との合弁会社を設立すると、その会社から継続雇用する者に対しては、設立時に雇用契約を締結し直さないと前会社における勤務年数が通算されることになる。その結果、終身雇用を保障される人が相当数出てきた。
広州地区は機械操作を中心としたオペレーション業務が中心であるが、「1年単位」で雇用していたときには危機感を持って働いていたのが、定年まで保障されるとなると、慢心して生産性が落ちるケースが出てくる可能性がある。これらの問題点に対する対策が急務の課題となっていた。
●上海地区
上海は営業拠点の中心であり、優秀な人材に対する不足感の非常に強い地区である。そのためには、「採用した優秀な人材のリテンション(引き留め)」が大きな問題点としてあった。また、このこととも関係するが、評価に対する満足度が低かったこともあり、「業績評価制度の改善」が重要課題となっていた。
また、処遇の決め方が個人ごとになっており、納得感が得られていなかったので、「オープンな処遇制度の構築」も同時並行して行う必要があった。
●大連地区
大連地区の工場は、89年に国営企業との合併から始まった。そのため、国営企業の賃金体系の考え方を引きずっており、「年功型の評価」が問題点として浮き彫りになっていた。
特に、若い層から年功型評価に対する不満が出ており、それは同時に「周辺他企業との賃金水準の格差」という問題も引き起こしていた。事実、この点を理由に辞めてしまう人が少なくなかった。
大連地区の仕事は精密部品の研磨など、熟練度を要する技術が不可欠である。SII ではこの事業を大連地区へと製造移管している関係上、その技術が同地区に根付いていかなければならない。「技術・技能レベルの向上・伝承」が、大連では特に課題としてクローズアップされていた。
人事労務管理に対する「考え方」
「地区ごとにそれぞれ問題点の特色はあるものの、やはり中国における人事労務管理の基本理念は共通であることが大切です。ただし、この点を強調するあまり、多くを要求するとかえって複雑になり、ローカルスタッフの理解が得られないと思い、以下の2つのポイントにシンプルにまとめました」(山下氏)。
・個人の能力・成果と処遇を連動させる
・社員のモチベーションを高め、組織の活性化につなげる(社員が元気の出る制度)
ちなみに、SII は03 年度から人事処遇制度を改定し、年功的、属人的、定昇的な考え方を廃止した。そこでは人材育成に重点を置き、目標達成度で業績を評価するなど、メリハリのある評価の実現を目指している。
そのために、評価に関しては「仕事」「顕在能力」「業績」の3つの軸で別々に決めている。仕事は「等級格付」、顕在能力は「本給ランク格付」という形で「給与」に反映される。業績については目標管理制度とリンクした「賞与査定」という形の運用を行う。
このように各々の評価のポイントが明確になることで、不透明な部分が一掃された。それは、本人のやる気、組織の活性化へとつながっていく。SI Iは03 年度末にはこの制度を導入し、SII のポリシーとして海外拠点へと展開していくことになった。「中国拠点における人事処遇制度の基本的な考え方もこれと同様のものとし展開していくことにしました」(山下氏)。
その際、海外拠点の新しい人事処遇制度を構築するにあたっては、「全世界共通」のフレームを用意し、そのうえで「中国共通」のフレームを別途適用することとした。

