経営活動の経験から学ぶ経営幹部養成コース「LGE」参加者座談会

管理者のリーダーシップ開発は、多くの企業にとって重要な育成課題の1つではないだろうか。その課題に応える研修として注目されるのが、リーダーシップ開発の研究機関CCL が開発し、日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)が提供する「ルッキンググラス・エクスペリエンス(LGE)」だ。 今回は、LGE 公開コースの参加者4名に、その感想を語り合っていただいた。(ファシリテーター:JMAM パートナー・コンサルタント CCL 認定LGE トレーナー 高井博夫氏)
 上野哲生氏
上野哲生氏トルンプ
ロジスティクス部
部長
小田原 達郎氏
ミネベア
人事総務本部
人材開発部
部長
安田卓史氏
ナブテスコ
総務・人事本部
総務部
参事
米田 真一郎氏
VSN
情報通信第2本部
テレコム第1事業部
事業部長
●お問い合わせ先
株式会社日本能率協会マネジメントセンター
カスタマーリレーション部
〒103-6009 東京都中央区日本橋2-7-1
東京日本橋タワー9階
TEL:03-6362-4343
FAX:03-6362-4664
E-mail:contact@jmam.co.jp
URL:http://www.jmam.co.jp
はじめに~LGEとは
LGEは、リーダーシップ開発の研究機関として欧米で高い評価を得ているCenter for CreativeLeadership(CCL)の研究者(組織行動学者)が、実在する米国ガラストップメーカー3社の協力のもと2年半にわたり開発した、経営幹部養成のためのプログラムだ。3日間のカリキュラムの核となるのは経営シミュレーション。参加者は、従業員5200名の架空のガラスメーカーの経営幹部として、社長、事業部長、工場長など、全員が異なる役割を担当する。
それぞれの役割によって異なる膨大な情報をインプットしたうえで、6時間20分の経営活動を実践。少人数のグループ編成で、折衝や意思決定活動を経験することにより、上位職に求められるリーダーシップ行動を実践から学ぶ。実践→振り返り→フィードバックのサイクルを通じて、自身のリーダーシップについての気づきを深める仕組みになっている。公開コースの他、社内研修として実施することも可能だ。
のめり込んでしまう研修
──研修に参加して、特に印象に残っていることは何ですか。
上野
3日間、かなり熱中して取り組みましたが、自分にとって気づきがあったのは参加者同士による「相互アドバイス」です。3日間を共に過ごした人たちから、社内では言ってもらえないようなことも、率直に言ってもらうことができる。それがすごくためになりました。
安田
研修が終わる頃には、本当に同じ会社の同僚じゃないかと思えるほど、さまざまな経営課題を皆で議論し、解決に向けて取り組めた、とても臨場感のある研修でした。詳細を知らされずに物事が進むので、次に何が起こるのか分かりませんから、のめり込まざるを得ない。しかも、事業部長という現実よりも上の役割でしたので、いろいろな気づきを得ることができました。
小田原
私は人材開発担当なので、社内で研修を行うことが多いのですが、この研修には、一般的なマネジメント向け研修との違いを強く感じました。1つは、安田さんも言うように、研修にのめり込める環境があること。そしてもう1つは、しがらみのない社外の人と一緒に学ぶため、遠慮なく率直なフィードバックを受けられることです。私の役割は製造部長でしたが、全く経験したことのないポジションでしたし、一緒にやるメンバーも知らない人ばかりのため、必死にやっていると、どうしても素の自分が出ますので、自分の振る舞いに対する気づきが得られました。
米田
私の場合、初日の社長を決める選挙と、2日目、経営活動を始める時ですね。選挙で役職を決めるやり方は新鮮でしたし、社長に立候補して、選ばれた時は驚きました。経営活動を始める時は、何か説明があるのかなと思っていたのですが、何もなく、開始時刻になったらシーンと静まりかえり、皆さんの視線が一斉にこちらを向いたので、「やばい、これは何か切り出さないと」と焦りました。内容については、いろいろな事象が発生してリアルでしたし、スキルも経験も上の諸先輩からフィードバックを得られたのは良かったです。いただいたフィードバックのデータは、仕事で何か困ったことがあった時に振り返れるように、研修が終わった今もいつもカバンに入れています。

他者の振る舞いから学ぶ
──フィードバックの内容から再発見したことはありますか。
小田原
「小田原さんは、ずっと話し続けていて、相手が理解できていないことがありますよ」「意見を言いたかったのに、小田原さんがしゃべり続けるので言えなかった」とずばり指摘されました。普段、気をつけていたつもりですが、まだダメだったか、と気づかされました。職場の部下からは絶対に指摘されないことなので、とてもありがたかったです。
上野
会社では自分の立場があるので、わざと振る舞っている部分もあるのですが、研修は素で臨んだのに、社内にいる時と同様の指摘を受けたので、それが自分の本質なんだろうなと再認識しました。
安田
人の話を聞いたり、部下が話しやすい雰囲気をつくったりすることはできるんですが、必要な情報を引き出すためには、別のスキルが必要だと分かりました。
──他の参加者の行動を見て、印象に残っていることはありますか。
安田
自分はどちらかというと控えめなタイプなので、リーダーシップのある人の振る舞いを見ながら、どんな要素が必要なのかをチェックしていました。社長に立候補できること自体、リーダーシップがあると思いますので、米田さんや上野さんなど、立候補した3人はすごいと思いましたね。
上野
いつもの自分とは違うことをやってみようと思ったんです。
小田原
私は社長を務めた米田さんが一番印象深くて、普段とは違うことに挑戦し、何もないところから、やるべきことをつくって実行していたのはすごいと思いました。
安田
研修が終わる頃には、本物の社長に見えましたよ(笑)。
「教えない研修」からの学び
──この研修の特徴は「教えない」ところにあります。フィードバックはしても、それをどう受け止めるかは参加者に委ねられています。その理由は、リーダーシップはこうあるべきだ、という正解がないからです。それぞれの持ち味を活かしたリーダーシップがあるべきだという考え方に立っているのですが、このような研修についてどう感じましたか。
安田
私は総務部なので、社内で危機管理のシミュレーション訓練を行うんですが、答えのない中でどう対応するかという点で、この研修と通じるところがあると思います。実は研修中、「こういう時にうまくやる方法を教えてほしい」と思ったこともあったのですが、よく考えてみると、この研修ではうまく振る舞うことが目的ではなく、自分がどれだけ気づきを得られるかが重要なんですよね。
小田原
何か新しい仕事を新しいチームでやる時に、自分がどう動き、メンバーと互いに理解を深めながらチームビルディングをし、最終的にアウトプットを出すところまで持っていくか、その練習になったと思います。
米田
何も分からないまま大海原に放り込まれた時の対応力が養われました。研修で体験したことは、より上位のポジションになった時にも役立つと思います。
上野
互いの経歴も、どういうものを持っているかも分からない中で、それでも1つの目標に向かってチームにならなければいけない。そこがすごく面白かったですし、のめり込めた理由だと思います。最初は意見が全く合わず、「どうしよう」と思った段階がありましたけど、徐々に自分たちなりの合意形成のやり方ができていきましたね。
新任上長の訓練に最適
──研修で学んだことで、職場で活かされていることはありますか。
米田
部下へのフィードバックのやり方を変えました。相手が受け取りやすいように、相手の行動から自分が受けたインパクトを率直に表現することを意識するようになりました。
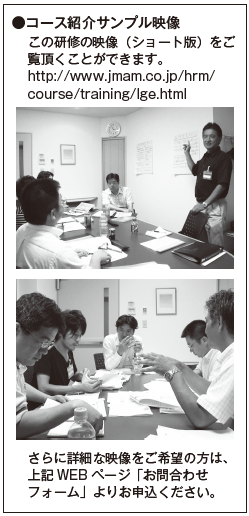
上野
研修での私の事業部のメンバーは、私が突っ走ろうとすると「ちょっと待ってください」とブレーキを踏んでくれたんですが、それが良い経験でした。職場では、部下は誰もブレーキを踏んでくれないので、自分だけ先走り過ぎないよう、少し待つ時間をつくるよう心がけるようになりました。それが一番の収穫です。
安田
研修を通じて、フィードバックの大切さを改めて感じました。先日、当社でも360度診断を実施したのですが、そこでも部下が求めているだろうと自分が想定していたことと、実際に部下が求めていることとの間にギャップがありました。その後は特に意識して時間を取り、部下と話をするようにしています。
小田原
初めて会った人たちと知らない環境で取り組む体験ができたので、実際に同じような状況になってもやっていける自信がついた気がします。この時の経験は、自分の部署に新たに異動してきた部下との接し方にも役立っていると思います。
──この研修を、どんな人に勧めたいですか。
上野
課長から部長、部長から本部長など、ポジションが1つ上がる方に向いているのではないでしょうか。失敗しても許されますから、次のポジションで挑戦したいことを試す場として非常に良いと思います。
小田原
組織の長として新たな事業を担当する前に、一度こういう場で練習してフィードバックを受けておくと、良い準備になると思います。
──本日はありがとうございました。
本記事に関するお問い合わせはこちら〔PR〕
- ●株式会社日本能率協会マネジメントセンター カスタマーリレーション部
- ●〒103-6009 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー9階
- ●TEL:03-6362-4343
- ●FAX:03-6362-4664
- ●E-Mail:contact@jmam.co.jp
- ●URL:http://www.jmam.co.jp