ビジネスパーソンは今、 なぜMBAで学ぶ必要があるのか?

グローバル化や次世代リーダー育成といった問題を持ち出すまでもなく、ビジネスパーソンはMBA を取得する理由がある。
企業の側にも社員をMBA に送り出す理由がある。なぜ今、MBA なのか。これについて、中央大学ビジネススクールの佐藤博樹教授にお話を伺った。
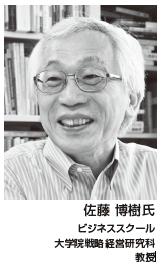 佐藤 博樹 氏
佐藤 博樹 氏ビジネススクール
大学院戦略経営研究科
教授
●お問い合わせ先
中央大学
戦略経営研究科事務課 ビジネススクール
〒112-8551 東京都文京区春日1-13-27
TEL:03-3817-7485(直通)
E-mail:cbs-info@tamajs.chuo-u.ac.jp
URL:http://www.chuo-u.ac.jp/academics/pro_graduateschool/business/
社員がMBAで学ぶ意味
ビジネス環境が不透明な今、ビジネスパーソンは自ら積極的に学び、エンプロイアビリティ(就業可能性)を高めていく必要がある。中央大学ビジネススクールで人的資源管理を教える佐藤博樹教授は、そのことについて次のように説明する。
「社員は、“今担当している仕事ができる”というだけではエンプロイアビリティが十分とはいえません。企業が直面しているビジネス環境を考えればわかりますが、不確実性が高く急激に変化する状況下では、“今の仕事内容が今後も同じ”という保証はありません。そのため、企業がビジネス環境の変化に対応することによって、今の仕事が持続的かつ不連続的に変わることを前提に、社員は自らのエンプロイアビリティを高めていかなければならないのです」
佐藤教授が述べるエンプロイアビリティには、2つの意味がある。
1つは、勤務先の会社が、ビジネス環境の変化に伴って事業内容やビジネスモデルを変えた時に、社員が新しい仕事に対応できる、つまり今の会社に勤め続けることができるエンプロイアビリティを確保すること。例えば、自動車メーカーに勤務していて、エンジン開発に10年携わっているエンジニアがいるとする。近い将来、すべてのエンジンが、モーターや水素エンジンに取って代わられているかもしれない。その時にガソリン・エンジンのことしかわかりません、他の仕事はできませんなどと言っていたら、企業はその社員を雇用し続けることはできない。
もう1つは、転職を考えた時にもエンプロイアビリティの向上が今以上に必要になる。今後、同業他社で今と同じ仕事に転職できる機会がますます少なくなることによる。自社だけでなく、同業他社も存続のためにビジネスモデルなどを持続的に変革するためだ。
いずれにしても、新しい事業構造やビジネスモデル、また新しい仕事に対応できる社員でなければ、企業は雇い続けることはできない。これからの社員に求められる職業能力は、変化に対応できる柔軟性や理論に裏づけられた幅広い応用力であり、それをどのようにして身につけていけばよいのか。その答えの1つがMBAの取得である。
「応用力を身につけるには、仕事の経験、つまりOJTで身につけた知識・スキルを理論的に整理し、“なぜうまくいったのか”などを理論的に整理し、理論に裏づけられた知識・スキルに変える必要があります。MBAでは、経験による知識・スキルを理論的に整理し、応用力のある知識・スキルとすることができ、5年後や10年後に、どんなに仕事が変わっても必ず役立つ能力なのです」「ハウツーは、仕事が変わればすぐに役立たなくなりますが、理論的に裏づけられた知識・スキルは陳腐化しません」(佐藤教授、以下同)
仕事の変化に対応できる柔軟な応用力などを身につける──これがMBAで学ぶ意味である。
社員をMBAに送る意味
企業の側には、社員をMBAに派遣することにどのような意味があるのか。
「ビジネス環境が変わる中で、企業もチャレンジをし続けなければ生き残れません。事業分野やビジネスモデルを変え、その結果、仕事が変わり、社員に求める職業能力も変化します。社員がそうした変化に対応できないのでは、企業としては存続が難しい。だからといって、そうした社員を外部から採用した社員と入れ替えることは簡単ではありません。社員が、将来の仕事にも対応できる職業能力を身につけてくれることが、企業にとって望ましいのです。柔軟に変化に対応できる職業能力を獲得している社員こそ、企業の競争力の源泉なのです」
他方で、企業が行っている能力開発は、通常、今の仕事に必要な知識やスキルを教え、今の仕事で結果を出すことを求めるものになりがちだ。さらに、企業としても将来の事業構造やビジネスモデルを先取りして、必要な職業能力の開発機会を社員に提供することが難しい。将来の変化を見通せないためだ。会社主導で“これを勉強するように”と特定の知識やスキルを社員に示しても、それが将来、必要になるとは限らない。そのため、会社にできることは、社員自身の主体的な学びを支援し、社員自身の学びをマイナスに評価しないことだけだ。
「社員がMBAに行って勉強したいというときに、時間的な配慮を行い、学びを支援すること。将来の変化に対応できる職業能力を身につけたいという社員は、会社にとって財産であるという理解が、経営陣だけでなく、管理職にも必要です」
会社にとって社員をMBAに送り出す意味は、変化への対応力のある社員=競争力の源泉を育てることなのだ。
MBAを取り巻く誤解
海外ではMBAを修了することで給与が上がるのに、日本では上がらない──これはMBAを取り巻く誤解だ。
「海外では、会社を辞め、フルタイムで通学し、MBAを取得して別の会社へ移ります。給与が上がるのは、転職でキャリアアップしたためです。日本でも自己都合で転職する人は、給与が上がっているのと同じです。一方、日本では在職しながら学び、修了後も同じ会社に在籍する人が多いので、MBAを取得しても自動的に給与が上がるわけではない。もちろん学んだことが仕事の成果に結びついたときには、給与や昇格にプラスになります」
MBAを学ぶためには、学費の負担も大きな問題だ。
「MBAでの学びは、社員自身がどこへ行っても通用する汎用的な知識を得るためのものなので、会社が費用を負担する必要はないのです。中央大学のビジネススクールは、厚生労働省の『専門実践教育訓練給付金』(最大で96万円)の支給対象コースとして指定されています。それに加え、奨学金制度も充実しているので、それも活用していただきたいと思います」
このように、国もビジネスパーソンの学びを後押ししはじめているため、こうした制度を活用しながら、5年後、10年後のキャリアために、今こそMBAを学ぶべきだろう。
MBAを学べる大学院を選ぶポイントは、学びたい職能分野に、理論と実務の両方に精通した教員がいるかどうかだ。在学中だけでなく、卒業後も続くネットワークを築けるか。働きながら通う以上、立地も重要なポイントとなる。資料を取り寄せ、公開講座に足を運ぶ──そんなところから始めてみてはいかがだろうか。
本記事に関するお問い合わせはこちら〔PR〕
- ●中央大学 戦略経営研究科事務課 ビジネススクール
- ●〒112-8551 東京都文京区春日1-13-27
- ●TEL:03-3817-7485(直通)
- ●E-mail:cbs-info@tamajs.chuo-u.ac.jp
- ●URL:http://www.chuo-u.ac.jp/academics/pro_graduateschool/business/